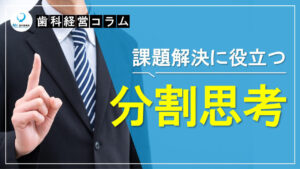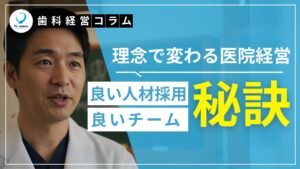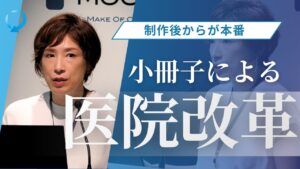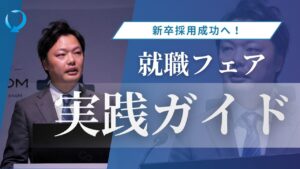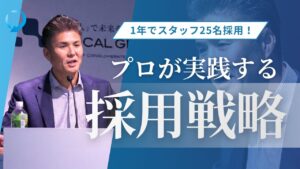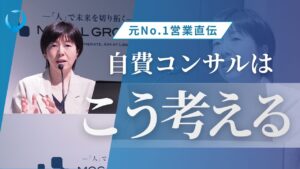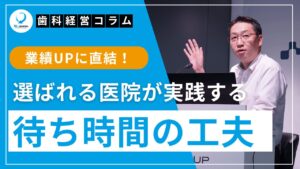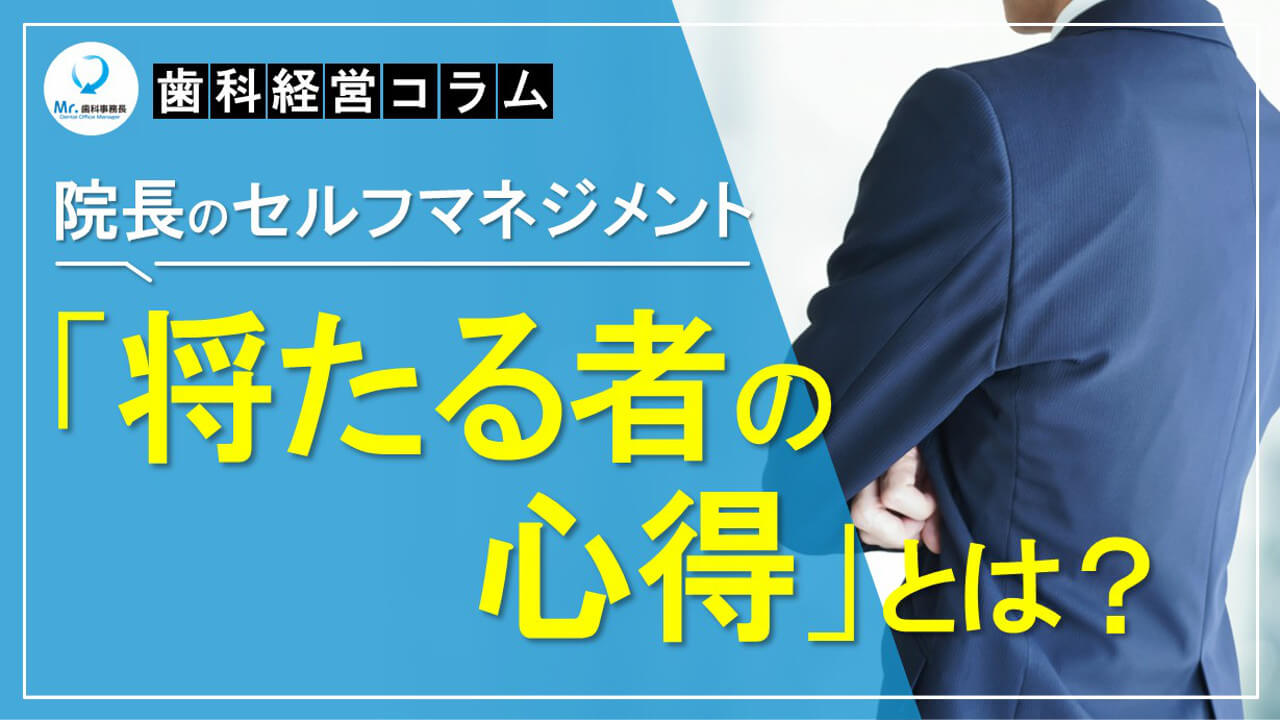
本コラムでは歯科医院のマネジメントに先立つ「院長のセルフマネジメント」のポイントについて紹介します。
最近「スタッフマネジメント」に悩んでいるという院長先生のお話をよくお伺いします。
歯科経営におけるマネジメント関連の書籍を読み、関連するセミナーも受け、コンサルタントの言うとおりに様々な「手法」を実践してみた。しかし、思ったように物事が進まない…。
スタッフマネジメントを効果あらしめる前提である「院長のセルフマネジメント」の論点について、成功している院長先生や歴史上の偉人の言葉をもとに考えていきます。
スタッフマネジメントがうまくいかないのは誰のせい?
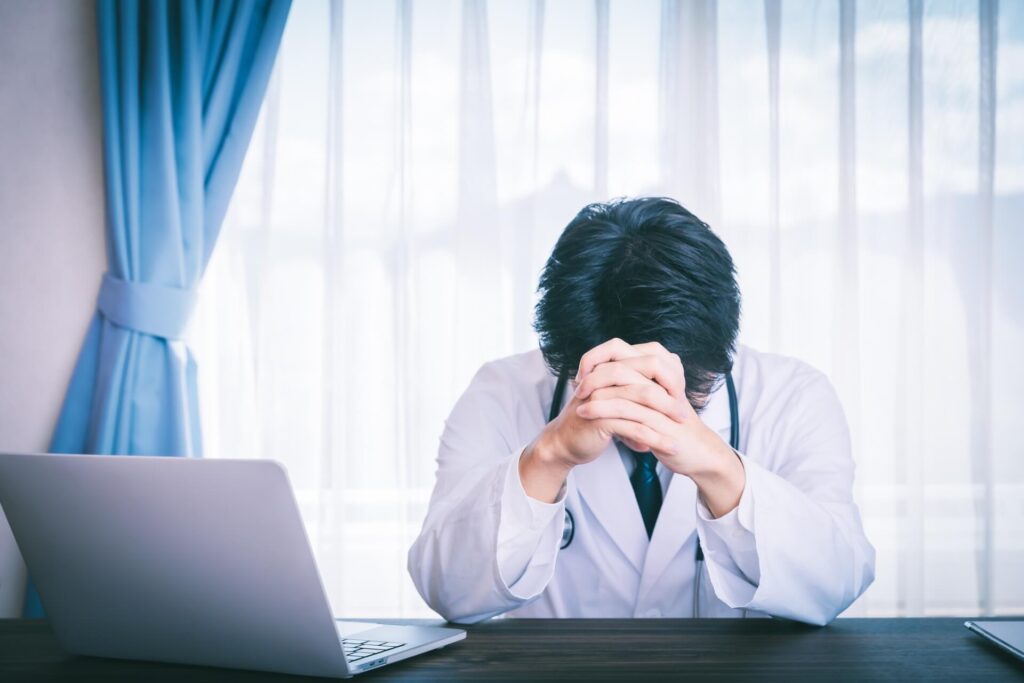
- もっとスタッフが自主的に考えて動いてくれればいいのに全く動かない
- コミュニケーションが重要と思い院長がスタッフの話を聞くと不平不満ばかりが出てくる
- 業績が伸び悩んでいる中、私語ばかりのスタッフを見て腹立たしさを感じている
同じような経験をお持ちの院長先生も多いのではないでしょうか。
経営者は孤独とよく言いますが、院長先生とて同じ。
経営者である院長先生のお悩みや気持ちはスタッフ様にはなかなか分からないものです。
スタッフマネジメントをうまく進めたいという観点から「マニュアルを作りたい」、「院内ルールを整備したい」、「評価制度を設計したい」、という相談をいただくこともよくあります。
こうした手法が全てうまく機能すれば歯科医院経営において大きな力になることは疑いの余地がありません。
ただ現場での実情を見ていると、評価制度やマニュアル作成など「管理的手法」で院内マネジメントを行おうとするも、実際にはモノが出来ただけで、うまく機能していないと感じることが多々あります。
挙句の果てには苦労して作ったマニュアルがどこにあるのかわからない、というような笑い話にもならないお話を聞くことまで。
構築した仕組みが良くないのか、在籍しているスタッフが悪いのか。一体何が原因なのでしょうか?
そんな中、ある院長先生からお伺いしたお話が印象的でした。
「医院経営のすべての責任は院長にある」
中々耳の痛いお話ではありますが、優れた経営者はそのように考える印象があります。
医院経営において自分以外の人間であるスタッフを自分の思い通りに動かすのは難しい。
そうであればスタッフを変えようとする前に、徹底的に「自己変革」することのほうがはるかに生産的であるとの考え方です。
内容はよくわかります。しかし、いったい何がうまくいかない理由なのか?そして何をどう「自己変革」していくことが必要なのか?自身のことに置き換えるのは、とても難しいことです。
将たる者の心得、自己変革の第一歩は?

有名な戦国武将である豊臣秀吉は「将たる者の心得」として、以下のような「自己変革」のヒントになりそうな言行を残しております。
わしが世の中をみるに、君臣朋友の間でも、みなわがままなところから不和になるようだ。
自分が好むことは他人が好まぬものである。家来でも同じで、いやがることが多い。将たる者はこの点に気をつけ、自分と同じような近臣を選び、ひそかに自分の目付として頼んでおき、ときどき意見をしてもらい、自分の行いの善し悪しを聞いて、万事に気をつけることが将たる者の第一の要務である。
この心得がなければ、自分の過失がわからずに、しだいにその過失は大きくなり、諸人から疎まれ、家を滅ぼし、身も失うものである
(出典:名将言行録 現代語訳 岡谷繁実氏)
これを院長に置き換えると、「お目付け役のスタッフに定期的に意見をもらう」のが「自己変革」の第一歩になるといえそうです。
院長を尊敬し、院長の理念や方針を理解したうえで、あえて厳しい意見を率直に伝えてくれそうな幹部スタッフに対して、「医院をよくするために率直にスタッフたちの思いや意見を自分の耳に入れて欲しい」と伝えることが、もっとも効果的な自己変革につながるでしょう。
豊臣秀吉に限らず、中国の古典で「名将」と尊敬され、国を立派に治めてきた偉人からは「諫言する部下を持つ」ことの重要性が繰り返し語られてきました。
とはいえ、こうした人材を得ることもとても難しいのが実情です。もし院内でそのような人材確保が難しい場合には、良質な意見役、外部のお目付け役として我々のような「アウトソーシング事務長」や経営コンサルタントを活用するのが一般的な方法の一つです。
このように、スタッフマネジメント、人材育成などに関しては、仕組み作りや各種制度設計など手法の活用も非常に大事ではありますが、その前にまずは経営者である院長自身が「自らを省みる」という姿勢を持つことがスタッフマネジメントの前提になっているといえるではないでしょうか。
ドラッカーが指摘するリーダーの資質とは

次に、歯科医院における将(リーダー)である院長は、スタッフマネジメントを有効に機能させるために、どのような「自己変革」を行えばよいのか、もう少し具体的に見えていきましょう。
ここではマネジメントの父とよばれるピーター F. ドラッカーの言葉から、理想のリーダー像を考える上でのヒントとなりそうな言葉を紹介します。
ドラッカーが「リーダーの資質に欠ける」と考えたリーダー像
- 人の強みよりも弱みに焦点を合わせる
- 「その人ができること」よりも「その人ができないこと」に注目する
- 当事者ではなく評論家としての振る舞いをする
- 「何が正しいか」よりも「誰が正しいか」が気になる
- 真摯さよりも頭の良さを重視する
- 有能な部下を恐れる
- 自らの仕事に高い基準を設けない
これらの項目を真逆に実践できれば、リーダーとしてマネジメントに成功することができるでしょう。
しかし実際に実践するとなると、自分の医院には理想的なスタッフなど一人もいません。
- 色々と院内のエラーにも気が付き助かるが、周りとの調和がはかれない。
- 人あたりがよく院内の潤滑油的な役割をしてくれるが、仕事の抜け漏れが多い。
- 院内で経験を積み長く安定的に在籍してくれているが、先輩としての意識が低く、後輩の指導などを安心して任せることができない。
ドラッカーの指摘は大事だと分かっていながら、そうは言っても、スタッフの言動に感情的になってしまったり、ついつい相手を変えたくなる衝動に駆られてしまう、といった院長も少なからずいらっしゃるかと思います。
そういった院長には「歯科経営出版」からリリースされているマネジメントオーディオブック『院長の経営成功術Vol.46 医療法人社団翔志会 理事長 武知 幸久先生の武知流「VisibleとInvisibleのマネジメント術」』のアンガーマネジメントの実践事例をご紹介します。ぜひご参考にされてください。

アンガーマネジメントによる自己変革と、スタッフ大量退職による危機からスタッフとの溝を埋め関係性を再構築したマネジメント術、そして緻密な分析と戦略によって、圧倒的なハイパフォーマンス医院を創られた貴重な具体事例を惜しみなくインタビューで公開いただいております。
こうした教材などもヒントに、一度院長自身の「将たる者の心得」について点検し、理想のリーダー像を研究されるお時間を確保されてはいかがでしょうか。
まとめ

本コラムでは、歯科医院のマネジメントを行うための土台である「院長のセルフマネジメント」について、豊臣秀吉やドラッカーの「将たる者の心得」の言葉を引用し紹介してきました。
- 自己責任/当事者意識
- 将たる者の心得(諫言する部下を持つ)
- リーダーの資質
理想の歯科医院運営を実現するために、「院長としての人間学(帝王学)」についての知識も、一つの経営リソースとして継続的に学ばれることをお勧めし、本コラムのまとめとさせていただきます。
みなさまの歯科医院経営のますますの成功と繁栄をお祈りしております。

この記事の解説者
Mr.歯科事務長
吉本 圭一 Keiichi Yoshimoto
兵庫県出身 血液型O型
大学卒業後、外資系スポーツアパレルメーカーの法人営業部でセールスの基礎を徹底的に
学ぶ。
30代半ばで通販会社を立ち上げる。代表としてWEBマーケティングやマネジメントに従事。その後、通販会社経営と並行して、3Dスキャナーの輸入代理会社を立ち上げる。
投資家からの資金調達・広報・マーケティング・経営戦略立案などの業務に従事し、実践力のあるビジネススキルを磨き上げる。
会社株式譲渡後にMOCALに参画。関西エリアに拠点を置き、歯科医院の経営・マーケティング・人事マネジメントなどに貢献している。