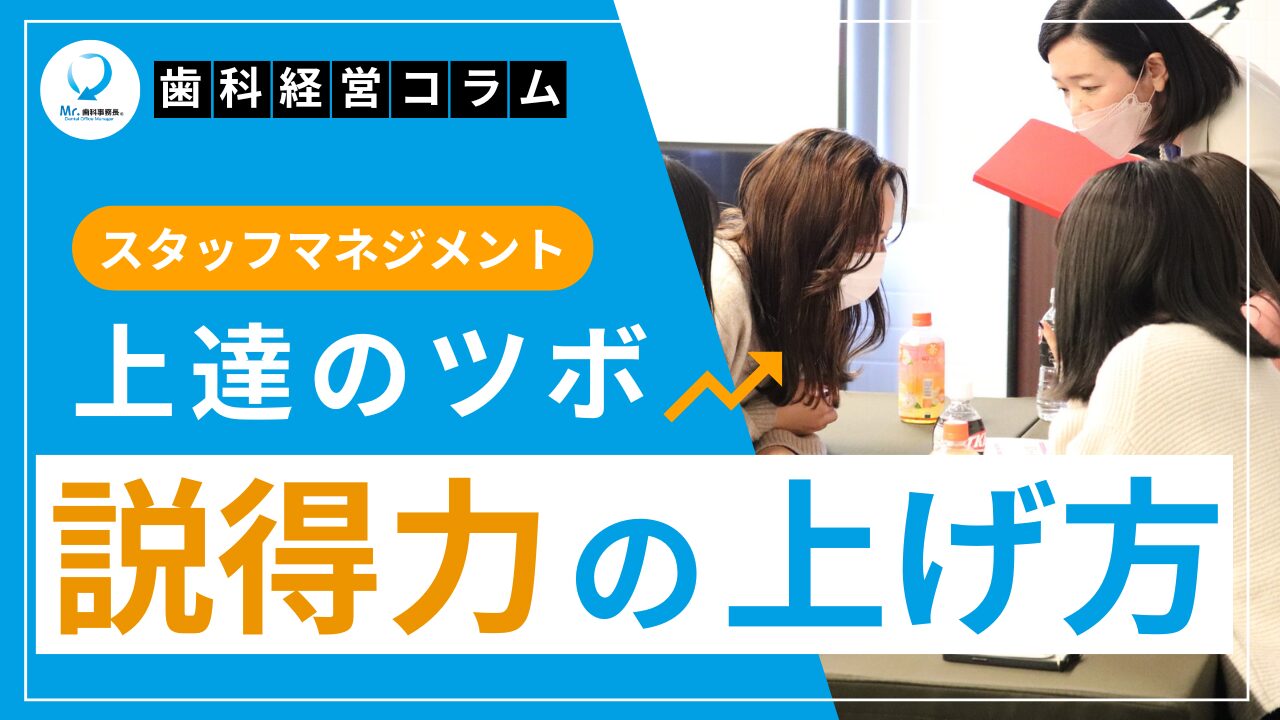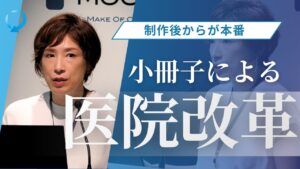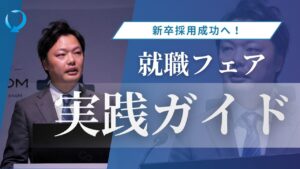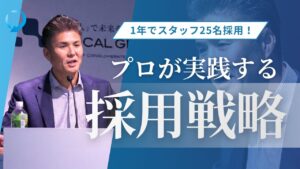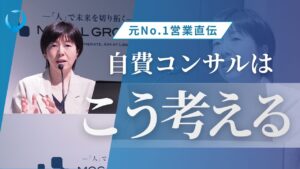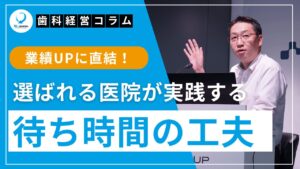このコラムでは歯科医院経営のお悩みベスト3に必ず入る「スタッフマネジメントに上達するツボ」についてご紹介します。
歯科医院を開業した多くの院長が、戸惑いや苦悩に遭遇することのひとつが「スタッフマネジメント」です。
院長が目指す医療コンセプトや仕事品質、また、職場生活や人間関係、チームワークなど、スタッフに期待をかけても、あまりにも理想とかけ離れ、最初は憤り、そのうちに疲れ、そしてある意味でのあきらめの境地を迎える、というケースが数多くあります。
昔から十人十色という言葉で表されているように、一人一人の考え方や志向性が違う人間が集まって、目的を共有し、一定の価値観や考え方に基づいて成果を上げていくためには「マネジメント力」が必要です。
この「マネジメント力」を構成する大きな要素の一つが「説得力」です。
使い古された言葉であり、真剣に向き合ったことがないという院長もいらっしゃるかもしれません。
本コラムではスタッフマネジメントに上達するツボともいえる「説得力」ついてご紹介します。ご自身の医院経営、スタッフマネジメントをチェックする視点として参考にしていただけると幸いです。
歯科医院あるある「院長とスタッフのコミュニケーションギャップ」
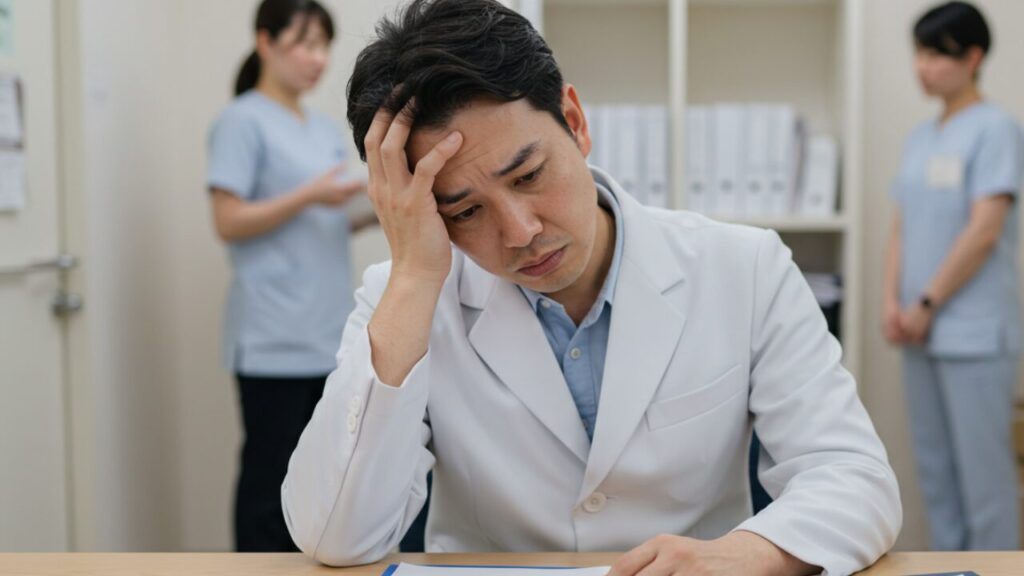
院長とスタッフには常に、コミュニケーションギャップが存在します。
「院長先生は思いつきで話す。言動に一貫性がない」
「忙しいのに、常に新しいことをやろうとして、結局途中でやめてしまう」
「売上の事ばかりいって、患者さんの事を考えていない」
現場ではこのような言葉をよく耳にしますが、一番忙しく、責任も重い院長としては「もう少し分かってくれよ。。」と愚痴の一つもこぼしたくなるのが人情です。
経営者である院長と、従業員であるスタッフとは「背負っている責任」が違うため、コミュニケーションギャップを埋めることは永遠に不可能と言っても過言ではないでしょう。
しかし、「経営とは人の力を使って事業運営すること」と言われているとおり、マネジメントを通じて成果を上げることは院長にとって逃げられない役割であり、そのためには、スタッフとのコミュニケーションを効果的に行うことが必須条件となります。
ではこのコミュニケーションを上手に行うために、何が最も重要なのでしょうか?
組織の長には「説得力」が必要とされる
その答えの一つが「説得力」です。
「説得力」とは、相手に理解させ、納得させ、行動の変容をさせる力です。
患者様への対応の仕方や、機材の取り扱い方、小さなことで言えば、ドアの開け閉めや歩く足音など、スタッフに改めてもらいたいと思うことは数多くあるのではないでしょうか?
また医院の成長や目標達成のために、アポイントの時間枠を戦略的に変更したり、決められたツールを使って患者さんへの情報提供の品質を上げるなど、新たな取組に協力してもらいたいことも多いでしょう。
このような院長の方針を構成メンバーに理解させ、納得させ、実行させるための力が「説得力」であり、この力が上がればマネジメントは格段にスムーズになります。
言葉による「説得力」

それでは「説得力」を上げるためにどのようなポイントを押さえていけば良いのでしょうか?
ひとつ目はやはり「言葉による説得力」です。
「なぜ、医療機関でも収益をあげる必要があるのか?」
「なぜ、スタッフであるあなた方は、院長の指示命令に従う必要があるのか?」
「なぜ、時間外の急患を診療する必要があるのか?」
「なぜ、診療時間外に、勉強やトレーニングを行う必要があるのか?」
こうした「なぜ」を自分なりに説得力を持って伝える技術が、人を使う上でどうしても必要なスキルのひとつと言えるでしょう。
言葉による説得力を上げる基本は「準備」です。これは誰にでも可能です。
スタッフに指示しようと思っている事柄について、人一倍考え、自分自身に必要性を「自己説得」し終わっているものであれば、自然に説得力のある言葉となります。
スタッフの前で考えを整理せずに指示を行い、正当な理由や説明もなく朝令暮改を行うことは、リーダーシップの源泉である信頼も損ねてしまいます。
まずは、しっかり自分の中で確信が固まるまで考えること。
ノートやパソコンなどできちんと文字に起こしてみる。また、スライドに整理するという作業を通すのも、自己確信を深めるコツの一つです。
その過程で、著名な書籍から論拠を探したり、他の医院の事例などを集めることで、説得効果が高まります。
言葉以外の説得力
歯科医院経営の現場を見ていると、それ以外の「説得力」の要素もあるようです。
- 例えば、「院長の怖さ」。これは単に「キレる、怒る」ということではなく、「仕事に対する厳しさ・真剣さ」が人格の雰囲気に出ているもの。
「この人は本気だ」と感じれば、それほど信念があって反対している場合を除けば、多くの場合スタッフは納得するものです。
- また「スタッフに高い基準を要求するが給料も高い」という「雇用条件」なども大きな説得力の一要素と言えるでしょう。
実際に、我々がサポートする医院でも「給与が高い」場合、多少、院長からむちゃぶりのような指示や方針と感じられても、スタッフはついてくる傾向が高いことを感じます。
- さらに、言葉には出ないものの、スタッフが「大切にされている。自分を重要視してくれている」と、院長の愛情を感じている場合、スタッフが院長をリスペクトしている場合にも、言葉を超えた説得力が働きます。
規模が大きくなり、スタッフ数も多くなってくるということは、院長自身の説得力も同時に、増していく必要があるのではないでしょうか。
一度、「説得力」という観点から、日常のマネジメントをチェックしてみてはいかがでしょうか。
説得力の前に、そもそも「士気」を下げていないか?

次に、説得力の反対にあるものについても考えてみます。
スタッフの「士気」について考えたことはあるでしょうか?
ちなみに「士気」とは、「戦いに対する意気込み。また、人々が団結して物事を行うときの意気込み。」と定義されています。
歯科医院では「モチベーション」と呼ばれていることが多いようですが、スタッフの「戦意」、組織の「勢い」と言ってもよいでしょう。
ドラッカーや松下幸之助なども愛読したと言われる有名な兵法書「孫子」を読まれた方も多いと思いますが、この中にも、『激水の疾くして、石を漂わすに至る者は勢なり。』など、「勢い」や「士気」を高める大切さがさまざまに説かれています。
歯科医院経営の現場でも「スタッフの士気」は重要です。
「メンテナンスの重要性を説明して、メンテアポを増やしましょう!」
「セラミックによる良質な治療を提案しましょう!」
「口コミによる紹介が増えるように、感動していただけるような接遇をしましょう!」
など、号令をかけても「スタッフが動かず。取組みが一向に進まない。」というご相談を数多くお受けします。
ここで説得が必要となりますが、そもそも、その前段階で、スタッフの「士気」を落とす言動がマネジメントの阻害要因になっていることも数多く目の当たりにします。
「士気」は人間の「心理・感情」に関わるものであり、これを上げるためのケーススタディは無数にありますが、私たちが歯科医院の運営サポートを行う中で「士気を下げてしまうケース」としてよく見かける院長の言動をご紹介します。
スタッフの「士気」低下を招く言動
スタッフの前で、別のスタッフの「悪口」や「愚痴」をこぼしてしまう
愚痴や悪口を聞いたスタッフは「自分がいない場所では、自分も同じように言われている」と考え、信頼関係を損ないます。
特に女性の場合には、客観的、合理的な事実よりも、愛されているか、認められているかという精神的な満足を高く評価する傾向にあるため、男性組織よりもより留意する必要があります。
うまくいかない状況を、人や環境のせいにして言い訳してしまう
スタッフは、院長に対して強いリーダーであってほしいという希望を持っています。
心情としては厳しいものがありますが、スタッフの前ではグッと口をつぐんだほうがよいでしょう。
指示や判断に一貫性がない(とスタッフに思われてしまう)
こう思われてしまうと、院長が指示をしても、しばらく様子を見るようになってしまいます。
「今回は本気で言っているのかな?いつもみたいに、あとで気が変わるかな?」と考えるようになります。
朝令暮改は経営にはつきものです。しかし、スタッフはそれを知りません。日頃から「いろいろな判断や指示をしているが、新しい情報が入ったり、周りの状況が変化しているため、その都度、最善と思う判断に変えることがあるのだ」ということを、教えておくことが大切です。
決めたことを、院長自身が守らない(とスタッフに思われてしまう)
院長自身がアポイントの時間までに出勤しない(遅刻)。
決められたサブカルテの記載ルールを守らない。
など、小さなことで士気を削いでいるケースは数多く見受けられます。
理由があって院長は行わない場合は、きちんと合理的な説明で、納得させることが必要です。
院内の問題や人間関係の悩みを相談しても解決してくれず、放置される
院長でさえも解決できないような問題であれば、もはやこの組織にいる限りこの悩み、問題は解決できない、と考え、退職に至ることが多々あります。
信頼できる中間管理職が育っていない段階での人事的なトラブルや問題は、院長自身が解決に当たる必要があります。
プライベートの事情が丸見え(スタッフの前で夫婦喧嘩をする。院長が浮気していることをスタッフが知っている)
院長への信頼、 尊敬が「士気」のもとです。電話、SNS、郵便物など、プライベートは見えないようにするなどの情報管理をお勧めします。
まとめ
このコラムでは、歯科医院のマネジメント力を高めるための「院長の説得力」と「士気を落とす言動」についてご紹介してきました。
こうしてみると、人間の集団を率いてマネジメントにより成果を上げていくためには、単にスキル論だけではなく、帝王学(院長にとっての処世術)や人格陶冶、公人の自覚、など、経営トップである院長に求められるハードルは高いものであることが分かります。
弊社の「Mr.歯科事務長サービス」は、上記のように経営者として重い責任とストレスを抱える院長が、自信をもって判断するとともに、スタッフマネジメントに多勢に無勢とならないようマネジメント支援させていただいています。
これまで、400件以上の歯科医院様の経営やマネジメント支援に携わってきました。特に「経営参謀プラン」では、歯科医院経営の事例を数多く知っている担当事務長が、院長の「壁打ち相手」となって、さまざまな課題への打ち手、課題解決のお手伝いをさせていただいています。
経営コンサルタントは「事例やノウハウ」にもとづいたアドバイスを行うのが中心ですが、Mr.歯科事務長サービスでは、さらに一歩踏み込んで、院長と二人三脚で「実務の実行」まで伴走しています。
理想の医院を実現し、地域へのさらなる貢献を目指す院長を支えるパートナーとして「Mr.歯科事務長サービス」の活用をご検討ください。
みなさまの歯科医院経営のますますの繁栄をお祈りしております。
この記事の解説者

MOCAL株式会社 代表取締役
今野 賢二 Kenji Konno
歯科業界歴25年。歯科医院向けソフト開発・販売のベンチャー企業で、マーケティング・営業マネージャーとして、販売の仕組みづくりの中心的役割を担い、トップブランド構築に貢献。