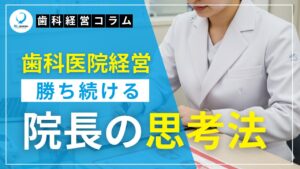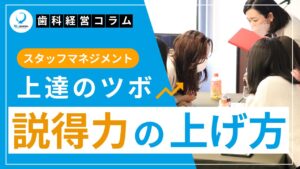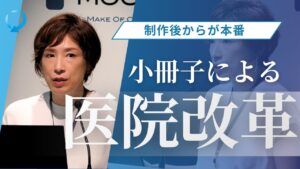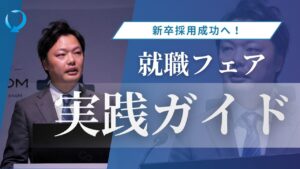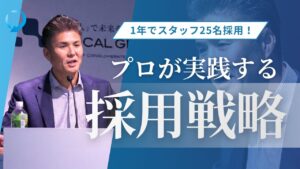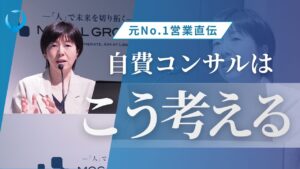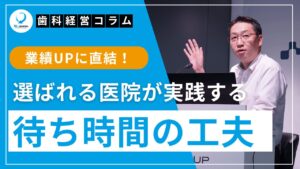このコラムでは歯科医院経営の成否を大きく左右している院長の「経営思想」、「考え方」の重要性についてご紹介します。
「経営思想」や「考え方」の大切さについては、松下幸之助氏や稲盛和夫氏をはじめ、数多くの経営者が、その重要性を指摘しています。
実際には「思想」や「考え方」は目に見えないものであり、その影響も「判断」や「行動」を通じ、現れるまでに時間がかかる傾向があること。そして、自分自身を客観視することの難しさから、何年も、何度も、同じ課題で足踏みしているケースが数多くあるようです。
今回は、具体的な事例にもとづいて、「思想」や「考え方」がどのように歯科医院経営に影響しているのかについての視点を紹介してみたいと思います。
特に、歯科医院経営やスタッフマネジメント“行き詰っている時“に、立ち止まって考えていただくための視点として参考にしていただけると幸いです。
成長や経営の限界は「院長の考え方」の限界

「どうしていつも同じような課題にぶつかるんだろう?」
「もう何年も業績は横ばいで壁を超えられない。。。」
「何度やってもうまくいかない、半分あきらめている。。。」
こうした問題意識をお持ちの院長もいらっしゃるのではないでしょうか?
20年以上、数多くの医院経営に携わる仕事をさせていただく中で、最近、特に感じることがあります。
それは「歯科医院の成長や経営の限界は、トップである院長の思想(考え方)」がつくっている、という事実です。
ある書籍にこのような例え話がありました。
「ワープロで手紙を書いてプリントアウトし、誤字に気づいたとしよう。
そこで、修正液を取り出して誤字を直したとしても、肝心のデータを直さなければ何度プリントアウトしても誤字は訂正されないままだ。
再度、プリントアウトしたあなたが、驚きのあまり、こう叫ぶ。
「そんなバカな。なぜ直っていないんだ。
いったいどうなっているんだ。狐につままれたようだ。」
要するにプリントアウトしたもの、つまり「現実」をいくら修正しようとしても、肝心のデータを正さなければ、誤字を直すことはできないのだ。」(「大金持ちになれる人」ハーブ・エッカー著)
そうです。このデータに当たるものが「院長であるトップの経営思想(考え方)」です。
「分院展開」の背景にある「経営思想」の違い
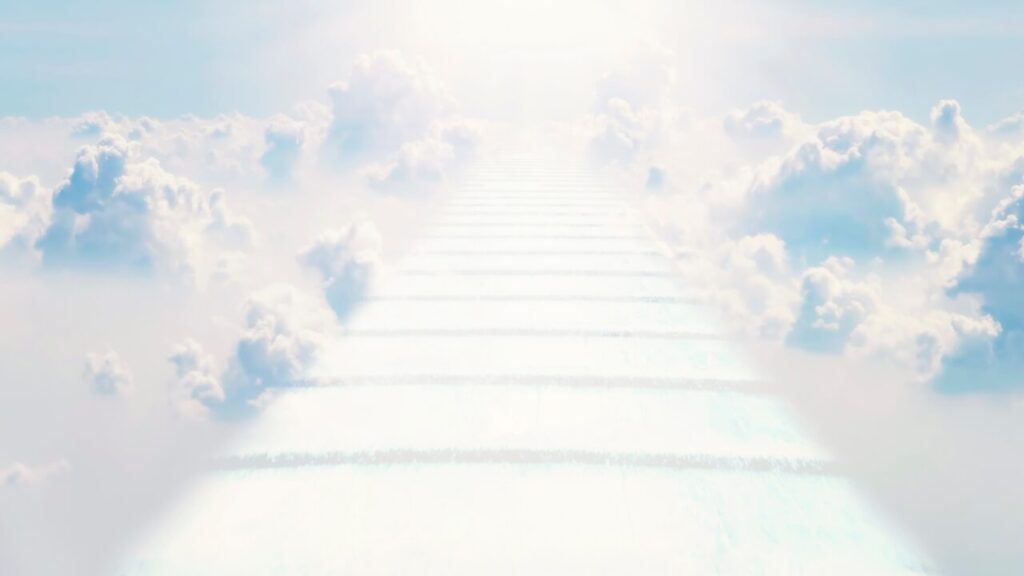
しかし、自分の思想が歯科医院経営にどう影響し、ボトルネックになっているのか?については、自分自身では、なかなか気づくのが難しいということは、私自身も深く感じています。
岡目八目という言葉がある通り、他人の事例を研究することで、自分自身の経営思想をチェックすることができます。
そこで事例として分かりやすい「分院展開」をテーマに「経営思想」の例をいくつかご紹介します。
資産運用型の思想
例えば、駅前にビルを購入して、テナント収入を得る。
そして数年後の値上がりを見込んで、ゆくゆくは売却益を得る。
という不動産による資産運用に似た思想を基に、分院展開をする事例。
開業費用は自分が投資し、分院長が稼いだ一部をその投資の利回りとしてとらえる、数年後、分院長に売却する。
システム化による生産効率の思想
マニュアルやシステム、制度により、平凡な人材でも一定のクオリティの作業を行えるようにすることで、分院を展開する事例。
人柄やリーダーシップなど、本来は「質的な面」を評価すべき項目も、「量(なにをどれだけやったか)」を基準に判定するという徹底した規格化・ルール・制度による管理。
「稼ぐことが本音」型の思想
人間の本音は「お金を稼ぐこと」という、シンプルな発想をベースに分院を展開する事例。
分院長が稼げる環境をつくり、手取り足取り指導をすることで、その後は、分院長の「稼ぐ」モチベーションで働き続けてくれる体制をつくる。
経営思想(考え方)にも長所と短所の両面がある
同じ「分院展開」でも、トップの思想にはさまざまな違い、個性があることが分かります。
もちろん、「思想・考え方」に応じて、実際の歯科医院経営に対する「打ち手」が代わり、その「結果」も変わってきます。
ここに挙げた3つのケースはどれも成功している院長のものであり、それぞれ「思想・考え方」には良い面があり、成果も出ます。
しかし、ある段階まで成長すると、そこで頭打ちになってしまいます。
例えば「資産運用型」の分院経営の場合には、歯科医院運営の舵取りを、医療理念ではなく投資効率で見ることが強くなり、医療の質の追求などは二の次になる可能性が高くなります。そのため、保険診療中心で付加価値が低くなる、構成員のモチベーションが低くなるなどのボトルネックが想定されます。
また、「稼ぐことが本音型」の分院経営の場合には、分院長の主たる関心が「自分の実入り」になることがあり、提供する医療サービスに対する倫理感が不足し、不正請求や、スタッフの定着率悪化などのボトルネックが想定されます。
成長の限界を突破するには「反対の考え方」を学ぶ

この限界を突破していくためには、「自分とは違う考え方」や、「自分と反対の考え方」から学ぶことが効果的であると言われています。
「資産運用型」の経営思想が運営上のボトルネックになっている場合には、医療の質にこだわっている院長の価値観や考え方、打ち手からを学ぶことで、次の成長のヒントを得ることができるでしょう。
例えば、しっかりとした「医療理念」や「運営方針」の明文化。ミーティングや各種イベント、教育プログラム等によるスタッフへの理念浸透の取組み。毎年の事業計画や目標に「臨床レベル」など「質の目標」や「成長目標」などを取り入れる。などなど。
単なる「資産投資」としてではなく、事業に命を吹き込み、維持するための仕組みをつくることで、ボトルネックを解決し、さらなる事業成長への道筋を描けるようになります。
成長段階に合わせた「考え方の成長」

今回、挙げた分院経営に関する経営思想の事例は、個性ある思想のごく一例です。
その他「人材」に対する院長の経営思想についても、
・従業員はコストである
・人件費は安ければ安い方がよい
・人は成長するリソースである
・従業員は家族である
・企業は人なり
・人は城、人は石垣
など、それぞれのトップの思想・考え方に基づいて、判断と実務処理が行われ、結果となります。
どれが良い悪いという価値判断ではなく、ある思想・考え方による限界が出た時には、別の思想・考え方から学ぶことで、次の成長・発展軌道を描くことにつながるということをお伝えしたく、紹介してみました。
成長の限界にぶつかっていると感じる方は、一度、自分の「思想」や「考え方」をじっくり点検すると共に、「違和感がある」と感じる、正反対の思想や考え方を持った院長から話を聞いてみること、研究してみることをお勧めします。
まとめ
このコラムでは、「経営思想」や「考え方」が歯科医院経営の成否に大きな影響を与えているという視点についてご紹介してきました。
自分自身の「思想」や「考え方」は、自分にとって、自然で当たり前であり、信念に根差していることも多くあります。こうした自分の当然の足場を、自分自身で点検するのは困難が伴います。
その為、多くの企業経営者は外部のアドバイザーとして、経営コンサルタント等を活用しています。
当社では「Mr.歯科事務長」サービスを通じて、400件以上の歯科医院様の経営やマネジメント支援に携わってきました。この中の「経営参謀プラン」では、歯科医院経営の事例を数多く知っている担当事務長が、院長の「壁打ち相手」となって、さまざまな課題への打ち手、課題解決のお手伝いをさせていただいています。
理想の医院を実現し、地域へのさらなる貢献を目指す院長を支えるパートナーとして「Mr.歯科事務長サービス」の活用をご検討ください。
みなさまの歯科医院経営のますますの繁栄をお祈りしております。
この記事の解説者

MOCAL株式会社 代表取締役
今野 賢二 Kenji Konno
歯科業界歴25年。歯科医院向けソフト開発・販売のベンチャー企業で、マーケティング・営業マネージャーとして、販売の仕組みづくりの中心的役割を担い、トップブランド構築に貢献。