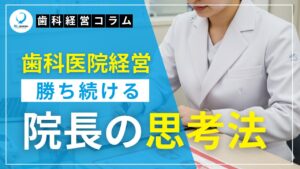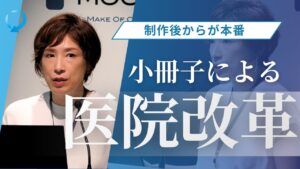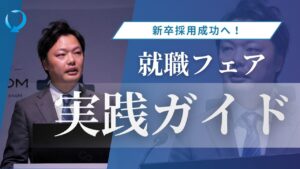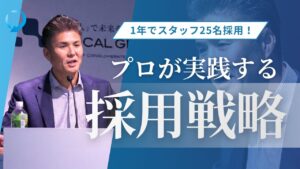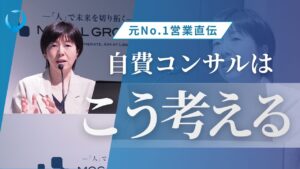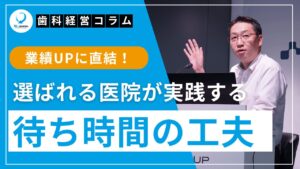このコラムでは歯科医院の分院展開が、マネジメントにどのような影響を与えるのか、分院展開する前に理解しておくべきポイントについてご紹介します。
歯科医院にも分院展開する大型法人が増えてきています。この背景には、医療機関である歯科医院にも市場競争が働き、二極化に拍車がかかっていることが挙げられます。
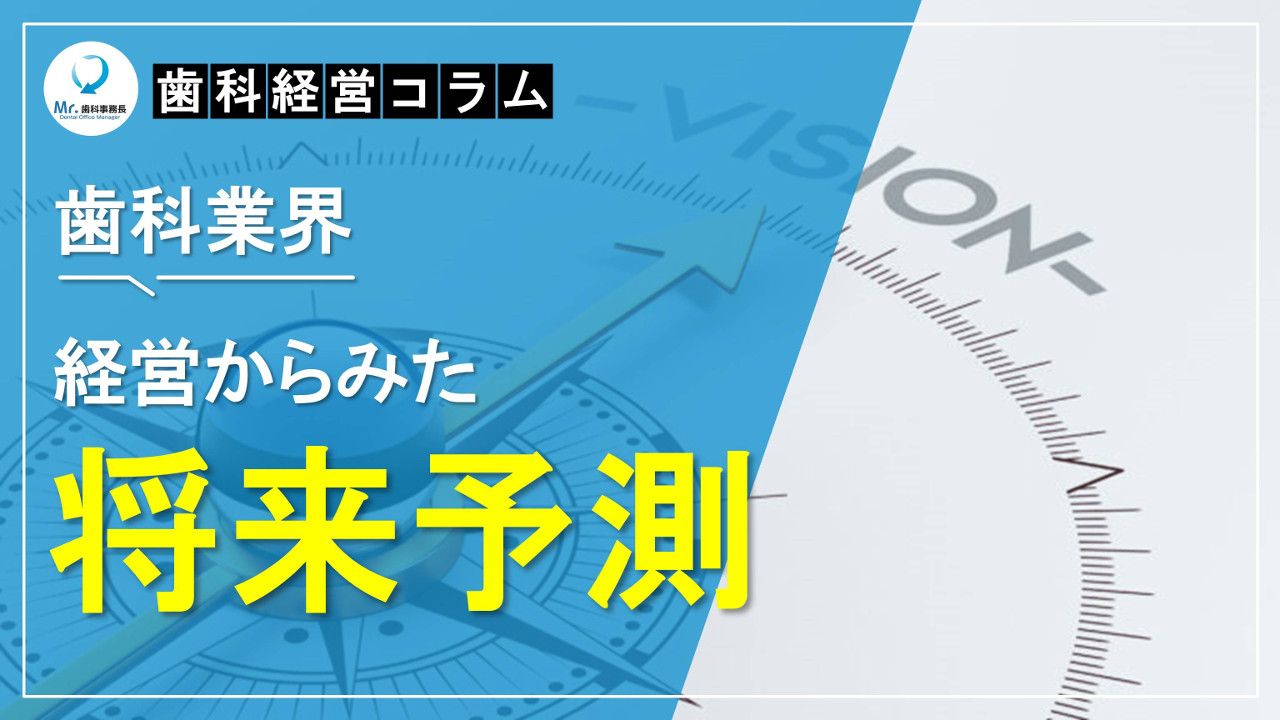
複数医院を短期間で展開する医療法人もあれば、1医院では上手くマネジメントできていても2医院目の分院を出した途端に苦境に陥るケースもあります。
分院展開する前に、マネジメント上どのような観点を意識しておかなければならないのか?を知っておくことで、分院展開を行うべきかの判断に役立てていただくとともに、分院展開を行うとした場合、どのような準備をしておけばよいのか?考えるきっかけとしていただければ幸いです。
分院展開すると経営がラクになるのか?

「分院長が稼いでくれれば、理事長である自分はラクになれる。」
という考えを漠然とお持ちの院長もいらっしゃるのではないでしょうか?
かく言う私自身もサラリーマン時代には、出世をし、部下を持つことで「もう少し、余裕を持って仕事ができるようになる」と考えていました。
しかし思い描いていた状況とは裏腹に、部下が増えるに従い、仕事はハードになるばかりでした。
そんな時に読んだドラッカーの書籍には次のように書かれていました。
「地位が上がるほど、管理のしようがない時間、しかもいかなる貢献ももたらさない時間の割合は多くなる。組織が大きくなるほど、組織を機能させ生産的にするための時間ではなく、単に組織を維持し、運営するための時間が多くなる」
組織コミュニケーションの法則として、組織の構成員同士が直接コミュニケーションした場合の手間は「人数の二乗に比例して増大する」と言われています。
つまり、「人が増えれば、ますます忙しくなる。大変になる」のが原則なのです。このことから、単純に、分院をつくることで経営や仕事がラクになるという発想は禁物です。
歯科医院における分院展開に必要な「組織化」

とはいえ、世の中には大きな会社を率いていても、あくせく時間に追われていない経営者も数多くいます。
ここにはどんな秘訣があるのでしょうか?
その秘訣は、結局のところ「組織」をつくるということです。
「組織」とは簡単に言えば、共通の目的を達成するために協力する集団であり、それを支える仕組みと考えれば良いでしょう。
分院展開の際に意識すべき「組織化」には以下の要素が挙げられます。
- 事業モデル
- 運営の仕組み
- 運営組織
- 経営担当者/マネジメント人材
個人医院からスタートし、分院展開を検討しよう考え始める段階では、組織ができていることは稀です。
事業規模が大きくなってきたとはいえ、この段階では、院長自身が「鍋蓋型(なべふた)型マネジメント」で、現場に細かく指示を出したり、一人で判断をしています。
鍋蓋(なべふた)型マネジメントの限界

組織ができていない状態で医院規模が大きくなり、分院展開に踏み切ると、次のような状況が起きてきます。
- やるべきことに手が回らなくなる、多岐にわたる取組みを管理できなくなる
- 院内のスタッフで運営するには、質、量ともに限界を感じる、スタッフに指示してもうまく物事が進まない
- こんなことも現場ではできていなかったのか?知らず知らずのうちに現場のレベルや生産性が下がってくる
- 特定の優秀なスタッフが産休に入るなどして、属人的な運営方法にリスクや限界を感じる
- 個々のスタッフが頻繁に院長に指示を仰ぎに来る、モグラたたきのようにいつまで経っても院長が対応しなければならない。運営にほとほと疲れる
- ごく一部の古参幹部と新しいスタッフばかり。新しいスタッフの定着が悪い、組織に安定感がない
- 院長と一般社員の意識の差が大きい、管理職が育たないため組織風土も馴れ合い的になってくる
- 結果、売上は伸びていても生産性や収益力が低下、分院は赤字基調で本院の利益で食いつなぐ形になる
こうした状況が示しているのは、「医院が小さな時から行ってきた鍋蓋(なべふた)型マネジメントの限界」であり、マネジメント体制(組織作り)が拡大に追いつかないために現れるものです。
収益性の高い「事業モデル」をつくる
事業モデルをつくるとは、簡単に表現すれば「売上をつくる」仕組みです。
特に、分院展開をするうえで重要な視点は、以下の二つです。
・「院長がいなくても一定の品質を維持できること」
・「生産性、収益性(利益率)が高いモデルをつくること」
分院展開で意識しておきたいのは、運営を維持するための余白(余裕)の部分です。
歯科医師や歯科衛生士、スタッフの急な退職への備えのために人員を余分に確保しておくこと。また、常時、院長の管理下にないため人事や労務面での手間暇がかかること。理事長ほどに診療品質が高くないためマーケティングなどの投資も多くなることなど、コスト構造は高くなると考えておく方が安全です。
その為には、やはり自費率が高い事業構造をつくらなければ、法人全体の運営にも影響がでることになります。
「不況・乱気流時代の手の打ち方」記事内にて「自費率アップへの打ち手事例」について記載しておりますので、こちらもご参考にください。

自費診療アップへの打ち手事例
どのような事業でも、顧客満足度を上げつつ、より収益性の高いサービス提供に移行する努力を行うことは、経営改善を考える際の基本的な取組です。歯科経営でいえば「自費診療」を増やす取組がもっとも即効性が高い取り組みの一つです。
この取り組みは、すでに多くの医院で取り組まれています。原則は「多様なニーズに応えるメニュー」、「情報提供(価値の説得)」、「オペレーションの効率化」の3つがあげられます。
多様なニーズに応えるメニュー
最近のトレンドとしては、急激にマーケットが広がっている「マウスピース矯正」や、子供の顎の成長と歯列を育てる「MRC矯正」など、時代のニーズをキャッチした新メニューに取組むケースが増えています。
臨床面での賛否の声はさまざまだが、ニーズに応えるという視点から、参考にしてはいかがでしょうか。
患者様に値上げと捉えられない形での値上げの方法の一つとして、新メニューの追加という方法をとるケースもあります。
「情報提供(価値の説得)」
「カウンセリングの強化」に、改めて腰を入れて取り組むという医院も増えています。
医療従事者の中には「自費のカウンセリング」という言葉に、「押し売り」をしているというニュアンスとして感じてしまうことが多いように見受けられます。
「良い治療を、熱意を持って勧めるということは、医療的な観点でも善である。」こうしたマインドセットをつくることに苦労するケースが多く見受けられるため、このコラムではあえて「価値の説得」という言葉を補足的に入れています。
「なぜこの治療方法があなたにとってメリットが高いのか」。こうしたことを、院長に代わって、スタッフが価値を伝えるための仕組み、人材養成を行うことは、とても投資対効果の高い取り組みです。
「オペレーションの効率化」
院長が「自費カウンセリング」を行うのが、もっとも成約率が高いのはどこの医院も同じでしょう。しかし「コア業務」に院長の時間を集中して生産性を上げるという観点から「トリートメントコーディネーター」や「コンシェルジュ」という説明役のスタッフとの「分業体制」を取るケースが、規模が大きくなるごとに増えてきます。
ここでの取り組みのポイントは「専任化」にあります。
多くの場合、効率化の観点から、受付や助手との兼任で行うケースを見受けますが、担当スタッフにとって「本業意識」が育ちにくく、思ったほど成果がでないことがあります。
適性のある人材を「専任化」すること、「ツール」や「トーク」を院長自身がチェックすること、時間や場所をきちんと確保すること、など、成果を上げるために適切なリソースを投下するという院長の意志決定が、早く成果をあげるためのポイントです。
分院運営の「仕組み」をつくる

次に、上記の「売上をつくる」という取り組みを「仕組み」にするという視点が必要になります。
簡単に表現すると、一連の仕事の流れや内容を「分業化」、「規格化」、「テキスト化」する取り組みです。
以下は、五十棲 剛史著「売上2億円の会社を10億円にする方法」で提唱されている事業の仕組み化の項目です。
(マーケティング面な仕組み化)
- 商品設計/②店舗設計/③集客設計/④営業設計/⑤実務設計/⑥アフターフォロー・クレーム処理設計
(マネジメント面の仕組み化)
⑦採用設計/⑧教育設計/⑨管理設計/⑩評価設計/⑪理念設計
こうした項目に基づき、仕事を合理的に分業し、規格や制度を定め、テキストとして明記する、という取り組みを行うことで、院長が細かい判断や指示を行わずとも、分院長やスタッフが、院長が定めた品質や方針に基づいた医療サービスの提供、組織運営を行えるようにしていくという発想です。
上記の各項目を、歯科医院運営で仕組み化する際のポイントについては、今後、別のコラムの中で紹介していきたいと思います。
分院を運営する「組織」をつくる
次に、必要なのは、上記の「売上をつくるための仕組み」を「改善し続けるための組織をつくる」という視点です。
(この考え方は、矢田祐二著「社長が3か月不在でも、仕組みで稼ぐ、年商10億円ビジネスのつくり方」で紹介されているものです。分院展開をする方にはお勧めの参考書籍です)
大事なポイントは、最初の仕組みは院長自身がつくることが大切ですが、「仕組みの改善」は、社員(分院長や幹部スタッフ)が行っていけるような体制を育てていくという点です。
弊社では、3億~10億の医療法人様向けに「DSO(Dental Service Organization)®」というサービスで、事業運営、特に組織づくりのマネジメント支援を行っています。
多くの医療法人の「組織づくり」サポートで実施する取り組みには、以下のようなものがあります。
- 理念、方針、考え方、目的、目標の浸透
- 組織図、期待役割、担当業務(役職・分業)の明文化
- 面談、1on1
- 勉強会、症例検討会、課題図書
- 各種ミーティング(事業推進/情報共有/育成目的のプロジェクト活動)
- コミュニケーションツール導入・活用
- PDCAサイクルの運用
- 管理職の養成(目標の達成、仕組みの改善)
- 次期管理職の発掘と育成
- 組織カルチャーの醸成(kick off等のイベント、定期行事)
分院展開を行う場合には、これまで以上に「組織立ったコミュニケーション」が必要となります。
家屋の建築イメージで例えれば、これまで1医院で運営してきた場合を「平屋建て」に例えると、分院展開をするのは2階建てや3階建て、さらには10階建てのビルなど大きな建築物になっていくようなものです。
建築物の基礎の作り方も違えば、木造から鉄筋コンクリートなど素材も工法も大きく変わってきます。
組織のコミュニケーション方法も同様に、内容やプロセス、方法や頻度など、目指す組織体制に相応しいものに成長させていかなければなりません。
経営担当者/マネジメント人材をつくる
次に最も大切な視点が「経営担当者/マネジメント人材」をつくるという視点です。
実際には、ここがボトルネックになっているケースが一番多いのが実情のようです。
経営担当者をつくるとは、分院の事業運営に対して責任感を持ち、一定の判断力やスキルをもった院長(理事長)の分身をつくることです。
これは頭では理解するのは容易ですが、実現するのは容易ではありません。
なぜなら歯科医院の事業モデルの特性として、歯科医師として優秀で、かつ事業運営やマネジメントの能力をも持っている人材は、自分で開業をしたほうがキャリア上有利でだからです。
実際に多店舗運営に成功している医療法人の成功要因は、この部分にどのような工夫や発明を行うかにかかっていると言っても過言ではありません。
例えば、ある医療法人では、5年後に分院を比較的安価な価格で売却するという条件で、優秀な分院長を継続して獲得しているケースもあれば、開業するより魅力的な高い処遇を提示しているケースなどもあります(その場合、それを提示できるだけの高収益事業モデルをつくることが前提)。
また、そこまでできないケースで多いのは、診療の品質担保は分院長の役割とし、運営や人事的なマネジメントは、チーフや事務局のエリアマネージャーなどマネジメントスキルのポテンシャルを持った人材との組み合わせでカバーするというものです。
事業成長に応じた人材戦略、マネジメント人材の活用については、「歯科医院のマネジメントとは? ~成長する歯科医院の人材戦略~」も参考にしてください。
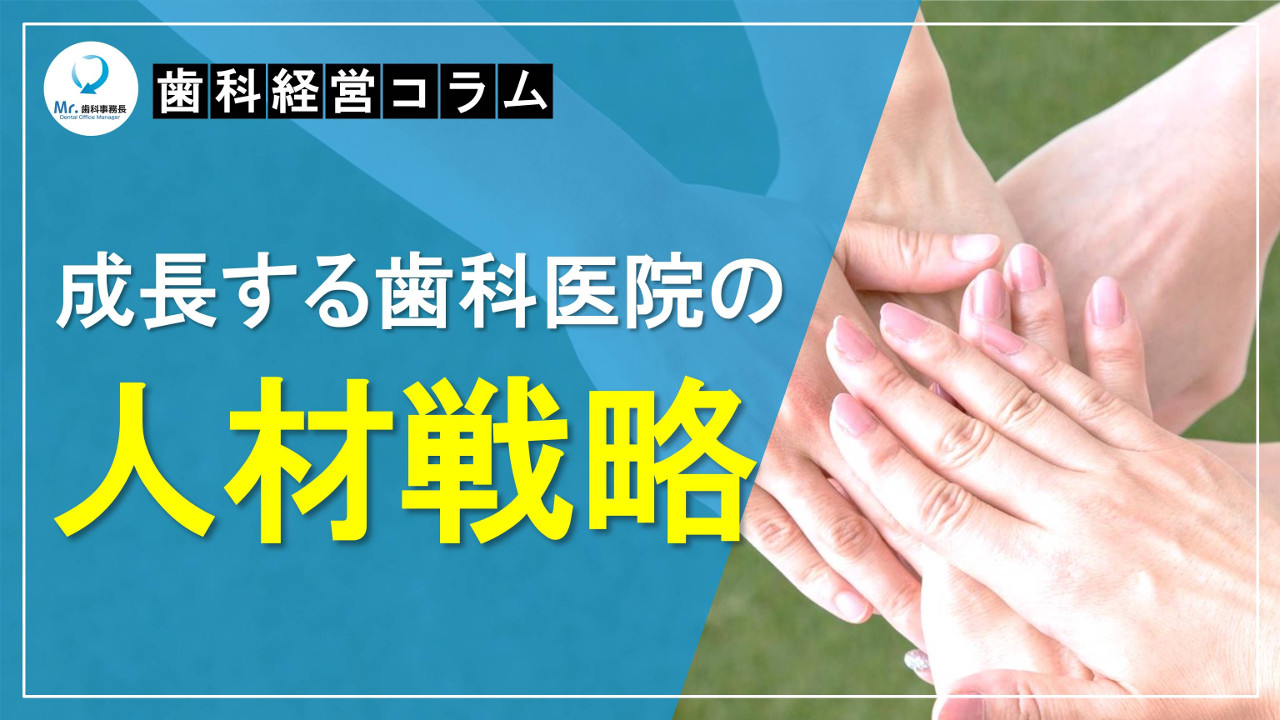
有為な人材を引き付け、養成していくという取り組みこそ、分院展開の成功の最も重要なキモと言えます。
有為な人材を引き付け、養成していく為には、院長(理事長)自身がもう一段マネジメント力を向上し、より大きな器となり、人材を育てていく教育者としての役割を果たす努力と時間が必要です。
院長(理事長)の役割・自己認識の成長
さて、ここまでの内容を見て気がつかれることと思いますが、分院展開を行うということには、院長(理事長)自身の役割が、臨床家から経営者に重点が移っていくことであり、自己認識も変わっていくことが求められます。
当然のことながら「経営」や「マネジメント」は、臨床とはまるで違う知識とスキルが必要です。
その意味で、「経営」や「マネジメント」について、これまで以上に真剣に、大量に学んでいくことが分院展開をするためには必要です。
しかも昨今の歯科医院をとりまく経営環境は、人材不足、コスト高、コンプライアンス順守、従業員満足など、さまざまな逆風のなかにあります。
壁に当たっては、その都度、それを乗り越えるための方法な何かないか?と、さまざまな情報や人脈を求めたり、夜も眠れず考えることで、ようやく一歩一歩、前進するような地道な取り組みが求められます。
こうした観点を踏まえ、分院展開に乗り出すには、それだけの「強い動機」が必要です。困難は承知で規模の拡大を目指すだけの動機、志は何か?このような問いを分院展開の前に行っておくことが、分院展開成功のカギを握っていると言えるのではないでしょうか。
まとめ
このコラムでは、歯科医院の分院展開を成功に導くポイント、分院展開を目指す院長(理事長)が事前に押さえておきたいポイントをご紹介してきました。
- 鍋蓋(なべふた)型マネジメントの限界
- 収益性の高い「事業モデル」をつくる
- 分院運営の「仕組み」をつくる
- 分院を運営する「組織」をつくる
- 経営担当者/マネジメント人材をつくる
- 院長(理事長)の役割・自己認識の成長
これらの取り組みを一般のビジネスで表現すれば「個人事業」から「会社経営」への成長と言えますが、これができるためには、繰り返しになりますが、経営者自身にそれを成し遂げるための志、知識、スキル、努力が必要とされるということです。
それを前提にした上で、機能をアウトソーシングで補うということは、一般企業でも幅広く浸透してきた経営手法の一つです。
弊社では、3億~10億の医療法人様向けに「Mr.歯科事務長『事務局』アウトソーシング」というサービスで、事業運営、特に組織づくりのマネジメント支援を行っています。

マーケティング、採用、人事、労務、経理、接遇指導、カウンセリング指導、幹部養成、組織運営など、ビジネス経験や数多くの歯科医院サポート経験を持ったメンバーがチームとなって、医療法人の分院運営を支え、組織づくりをサポートしています。
医療法人の本部機能をいち早く手に入れる方法の一つとして、ご検討ください。
みなさまの歯科医院経営のますますの繁栄をお祈りしております。
この記事の解説者

MOCAL株式会社 代表取締役
今野 賢二 Kenji Konno
歯科業界歴25年。歯科医院向けソフト開発・販売のベンチャー企業で、マーケティング・営業マネージャーとして、販売の仕組みづくりの中心的役割を担い、トップブランド構築に貢献。