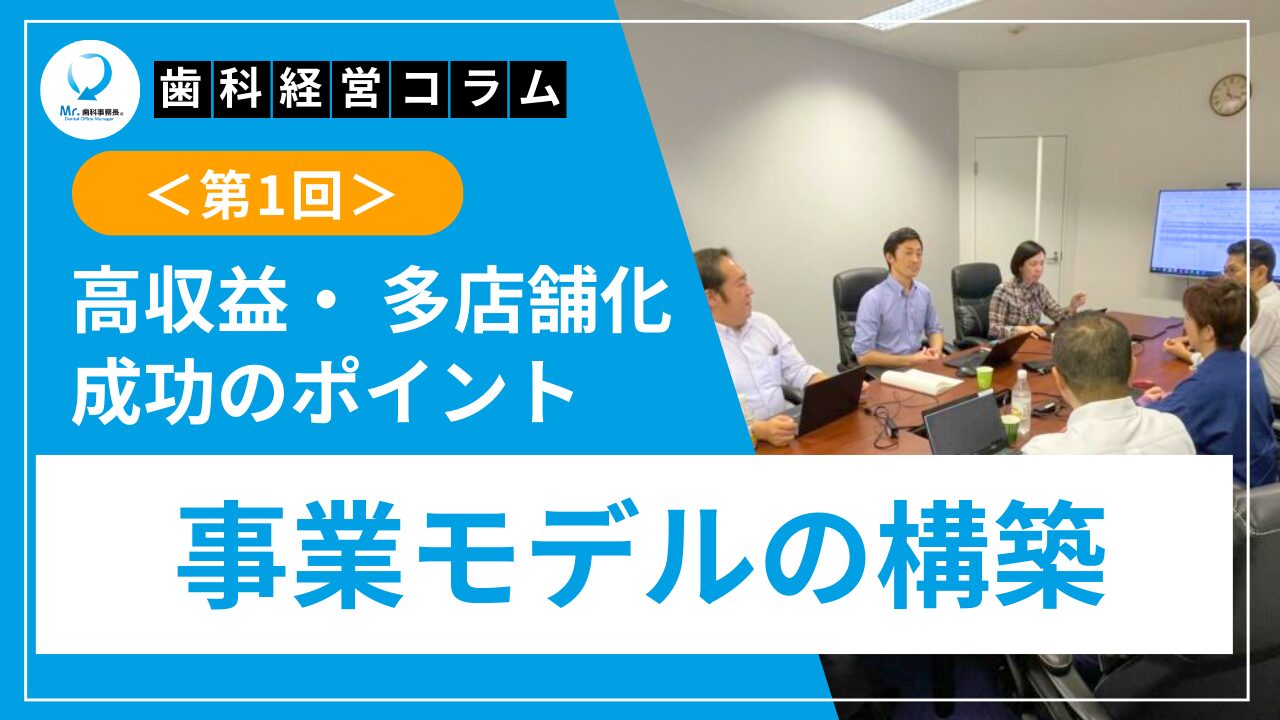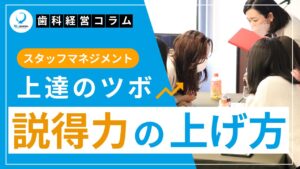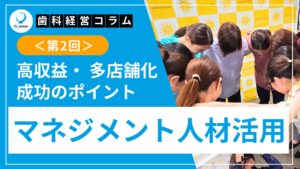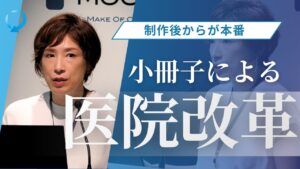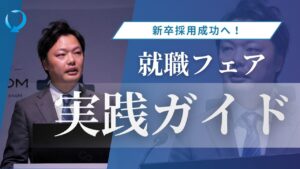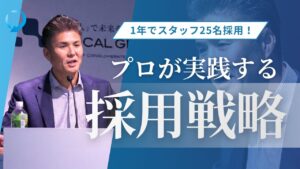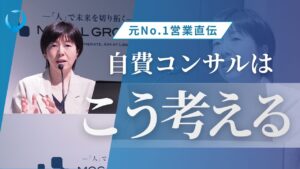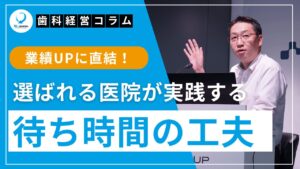このコラムでは「大型化・多店舗化に成功する歯科経営のポイントとは?」と題し5回に分けて情報をお届けしていきます。
昨今、歯科医院にも「多店舗化」「大規模法人化」を志向する組織が増えています。
その背景には、市場競争による「二極化」があります。歯科医院数の推移は、2015年の68,737軒をピークにそれまで増加してきた軒数が減少に転じました。
人口の推移や国の施策などさまざまな要因がその背景にありますが、マーケットのニーズに対して供給が「飽和」の段階に入ったと考えられます。どのような商品・サービスにも共通しますが、需要に対する供給が飽和した場合、「市場原理」がより鮮明に働きだします。
簡単に言えば、サービスの優劣が比較され、その結果、差が開いてくるようになってきます。
さらにもう一つ「不況期には、二極化の差がさらに大きくなる」と言われています。不況期の「経営判断」や「マネジメントの巧拙」は、好況期よりも、業績や組織の成長に大きな差となって表れてきます。
現在もまた「失われた30年」、コロナパンデミックや戦争に端を発した乱気流の時代で景気下降局面が続いています。
いまがまさに「優勝劣敗の法則」がダイナミックに働き、マネジメント巧拙による二極化の開きが一層大きく表れるタイミングにあると言えるでしょう。
この優勝劣敗の中で着実に成長を続け、5億~10億規模の事業体として成功していくための歯科医院経営のポイントについてご紹介していきます。
ビジネスモデルを構築する3つの要点
まず「多店舗化」「大規模法人化」をしていくための条件について考えてみましょう。
ある経営コンサルタントは「年商2億までの会社の社長は、優秀な個人事業主である」と指摘しています。
院長が優秀なプレイヤーとしてクリニックを切り盛りするスタイルの場合、臨床のスタイルによって多少の違いはありますが、やはり2億程度の事業規模が限界ではないでしょうか。
この限界を超えて大きくなるためには何が必要なのでしょうか?
この時に必要なのは、院長自身が「もっとも優秀なプレイヤー」であるという「ある意味での心地よい状態」から脱却し、経営者として「ビジネスモデル」を構築することが自分の仕事であるという「発想の転換」「自己認識の転換」をすること。
そして「ビジネスモデルを実務に落とし込むこと」です。
では、次にビジネスモデルとして落とし込むべき3つの要点を見ていきます。
マーケティング・集患力

どんな事業でも「新規顧客」がいて、「リピーター」になる仕組みがあれば成功すると言われています。
現場に自分いなくても、この「新規顧客獲得」と「リピーター獲得」の二つが「仕組みで増えていく状態」を構築することが1つ目の条件と言えるでしょう。
このポイントについては、さまざまな手法が確立されているのでこのコラムでは詳細は省きますが、大規模化に成功している医院では、きちんとモデルとして構築され、自動的に成果が上がる仕組みが必ずできています。
この仕組みを構築するという実務の一視点として指摘しておきたいことは、大規模化に成功する院長、理事長は「投資判断が早い」「専門家を上手に活用する」という特徴があげられます。
過去の軍事的な教訓から「兵力(戦力)の逐次投入は愚策」といわれています。
旧日本軍がガダルカナル戦などで、強力な米軍に対し兵力を小出しにして次々に撃破されたケースを引き合いに語られることがありますが、中途半端な策を小出しにすることは、いたずらに時間やお金を消費するだけで、望ましい成果を上げることはできません。
「多店舗化」「大規模法人化」されている経営者は、「金額が高くても実績を出している業者を使う」「予算を小出しにせず一気に投下」し、まずは専門家を活用し、集患の基盤をいち早く構築していきます。
高収益の「売り物」を仕組み化する

2つ目の条件は、経営者が現場で手を下さなくても「高収益の売り物」が売れる仕組みを構築することです。
基本的に「高収益体質」のビジネスモデルを構築しなければ「多店舗化」や「大規模法人化」するための「投資体力」がつきません。
薄利多売型で収益力が低い場合には、銀行の借り入れ枠なども少なくなること、さらには組織運営の手間暇がかかることからスピード感のある展開は難しいでしょう。
この時に重要な視点としては、「数百万円の症例」を院長自身(または、たまにしか手に入らない優秀な勤務医)が行うスタイルではなく、院長の半分しか臨床技術がない勤務医でも自費売上があがる(もちろん患者さんも満足していただける)「売り物」を仕組みとして構築することです。
例えば、最近であればマウスピース矯正を「売り物」にしている医院も増えていますが「勤務医でも良質なサービスを提供できる仕組み」として構築していくことが重要です。
また別のスタイルでは「歯科衛生士によるメンテナンス」を「売り物」として磨いている医院も増えてきています。
ある医院では歯科衛生士が1人200万/月の売上をあげる仕組みが、高収益体質のキーになっています。
いずれにしても、経営者が直接、臨床的に手を下さなくてよいこと、属人的なものではなく仕組みとして稼働するように構築することがポイントです。
スタッフ採用・戦力化のための仕組み

3つ目は「提供体制」を仕組みとしてつくることです。
提供体制構築の実務は「採用」「教育」「組織文化の醸成」の3つです。
①採用
特に「多店舗展開」「大規模化」を目指す場合に押さえたいポイントがあります。それは「新卒」採用です。
組織が本当に盤石に発展していくのは、「新卒」から採用したスタッフが主力として活躍するようになってくる段階です。
こうしたモデルを構築するためには少なくても5年程度は手間暇をかける必要があるでしょう。
②教育
「人材は成長するリソースである」と言われている通り、戦略的に教育を行うことで一人当たりの生産性が高くなります。
また勤務年数が長くなり業務に習熟することも生産性の向上につながります。
収益力が高く、安定した経営を続けている医院の多くは「教育」や「コミュニケーション」に時間を惜しまない特徴があります。
「教育への投資(アポを切るなど)」は一見、売上の機会ロスにも見えますが、「多店舗化」「大規模化」に成功するためには「人材に成果を上げさせるための教育の仕組み」も必須条件の一つです。
③ 組織文化の醸成
組織文化は、その組織で働く構成員の「判断」や「行動」に大きな影響を与えます。
経営者に代わって、患者さんにサービスを提供するスタッフが望ましい「判断」や「行動」を行えるようにするために、意図的に組織文化の醸成を行うことが重要です。
組織文化を醸成するためのポイントを二つ紹介します。
- 一つ目は「価値観の教育」です。
具体的には「診療(経営理念)理念」「クレド(行動指針)」「仕事観」の明示です。
ただし、この時に大切な視点は、「経営理念」や「クレド」など、明示化も大切ですが、実際には、経営者や幹部が、本音レベルで日常的に何を価値とし、どういう言動をしているのか?が文化としてスタッフに伝播するという視点です。
- 二つ目は「論理を示すこと」です。
何かの案件について「経営判断」を行った際に、「なぜこういう判断をしたのか?理由や論理をセットで説明する」ことです。
これを繰り返すことで、「論理」が線路のレールのようにつながっていき、部下やスタッフが、トップの価値観をそれぞれの持ち場で実践できるようになります。
事務局(スタッフ部門・管理部門)を使えるか?

ビジネスモデルの次に重要な項目としてあげられるのが「事務局を使えるか?」です。
この事務局には「スタッフ部門」と「管理部門」という二つの機能が含まれています。
スタッフ部門は「経営企画」「人事」「マーケティング」「財務」など経営者の戦略機能を補完します。
管理部門は「経理」「労務」「事務」など経営者の管理機能を代行します。
この「事務局を使えない」ことが成長の足かせになっているケースは数多く見受けられます。
事業経営は「生産」「販売」「人事」「財務」「広報」などさまざまな機能で成り立っています。
それぞれの機能が同じパイプの太さで連携することで、事業が正常に成長をします。
診療現場で患者さんと接することをメインで経験されてきた院長、理事長の場合、診療部門は上手にマネジメントできていても、事務局を効果的に使えずに、成長のボトルネックになっていることがあります。
事務局を使えない理由としては、主に以下の2点が多いようです。
①間接部門にお金を投資する価値を感じられない
診療スタッフ以外の間接部門は「価値を生み出さないコスト部門」という発想が強く、診療人数を支えるための十分な「スキル」「人員」の事務方を使えていない。
②事務方の使い方が分からない
どのような業務に、どのような人材を活用すべきか。どのような条件で雇用すべきか。
事務局スタッフのマネジメントにどの程度、時間をかけるべきか。
こうしたことに未経験なために、使い方が分からない。
事務局への適材適所の人材配置、合理的な業務構築など、医療現場とは別の見識やスキルを身に着けることも「多店舗化」「大規模法人化」の必須条件と言えるでしょう。
まとめ
このコラムでは、大規模化・多店舗化に成功する歯科医院経営のポイントについて「事業モデル」の観点からご紹介してきました。
事業モデルの構築と一言表現できても、一つ一つのマネジメント実務は繊細で、落とし込みのためにはエネルギーや時間がかかるのは当然のことです。
冒頭でも触れましたが、「成長速度」を上げるための常套手段のひとつに、専門家(専門企業)へのアウトソースがあげられます。
弊社で提供している「Mr.歯科事務長」は歯科医院経営の実務を多岐に渡ってサポートする画期的なサービスです。採用、労務、人事マネジメント、組織構築から、院長の秘書まわりの事務、さらには集患などのマーケティング業務まで幅広くお手伝いしています。
事業拡大や組織の成長を目指す院長を支えるパートナーとして「Mr.歯科事務長サービス」の活用をご検討ください。
次回のコラムでは、経営者や人材論について考えていきたいと思います。
みなさまの歯科医院経営のますますの繁栄をお祈りしております。
この記事の解説者

MOCAL株式会社 代表取締役
今野 賢二 Kenji Konno
歯科業界歴25年。歯科医院向けソフト開発・販売のベンチャー企業で、マーケティング・営業マネージャーとして、販売の仕組みづくりの中心的役割を担い、トップブランド構築に貢献。