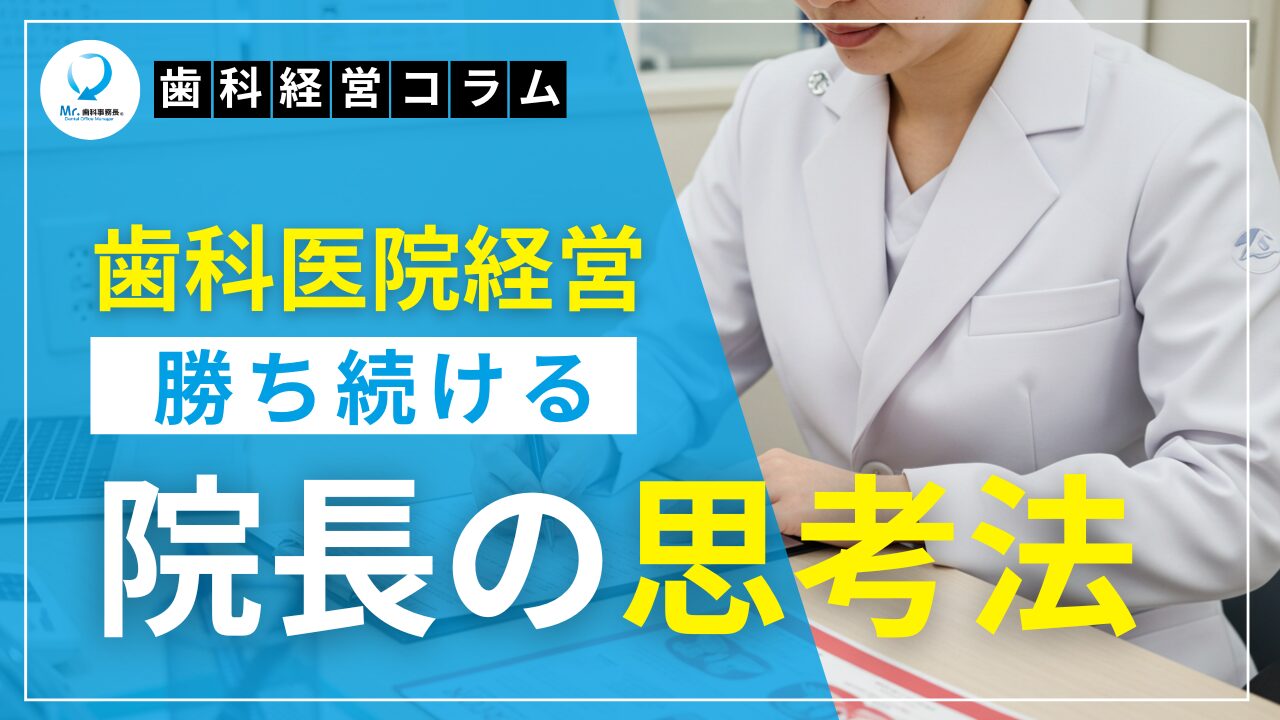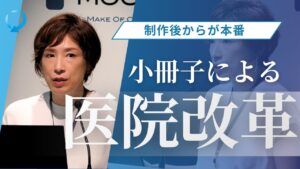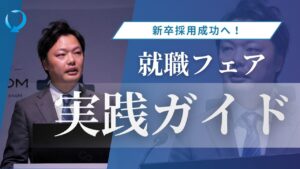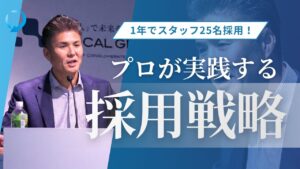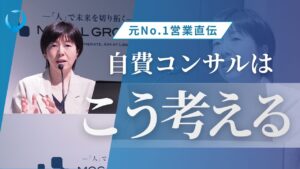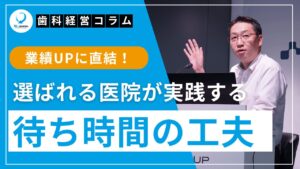このコラムでは歯科医院経営に勝ち続けている院長が持っている視点と考え方についてご紹介します。
「医院規模を成長・拡大させていきたい」という若手の歯科医院経営者が増えてきました。
一昔前は「開業すれば誰でも成功できる」という時代環境でしたが、昨今では、「差別化や経営努力をしなければ勤務医時代よりも収入が減る」という厳しい経営環境となりました。
こうした環境で、危機感や起業家精神を持たざるを得ないという背景が熱心な歯科医院経営者を生みだしていると考えられます。
厳しい時代でも堅実に医院を成長させ、事業拡大をしていくために、歯科医院経営の最終責任者である院長が押さえておくべき思考法について2つの視点をご紹介します。
特に「トラブルやクレームが続く時」、「成長が止まっていて、次の打ち手が見えない時」に立ち止まって考える視点として、参考にしていただければ幸いです。
「クレーム・トラブル・雑音」は見直しのシグナル
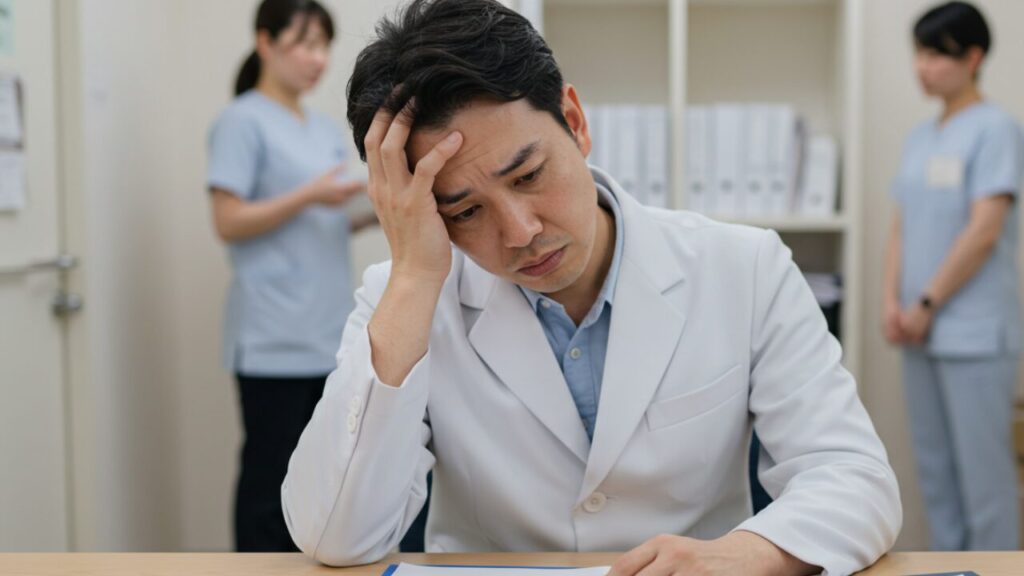
「最近、クレーム、トラブル、スタッフの退職が多いな~、、、」という時期を経験した院長も多いのではないでしょうか?
このような「クレーム・トラブル・組織内の雑音(退職やスタッフ同士のトラブル等)」が“立て続けに起きる時”は、医院運営や院長自身の考え方を見直すシグナルです。
・患者さんからのクレーム
・誤飲などスタッフによる医療事故
・スタッフの事故、病欠やメンタル不調
・院内の人間関係のトラブル(スタッフ同士の不仲、勤務医との男女間トラブル)
組織に「許容範囲を超えた負荷がかかっている」時に上記のような事象が続くと指摘されています。
求める成果に見合う努力と投資をしているか?

こうした状況は、大抵の場合「現在の実力以上の成果を求めていること」から生じます。
「実力以上の成果を求める」とは、手に入れたい成果と「努力や投資がバランスしていない状態」です。
「何とか早く成果を手に入れたい」という焦りの気持ちから、経営リソース活用のバランスを崩していることが多いようです。
クレーム、トラブル、院内の雑音など「最近ちょっとおかしいな?」と感じた時は、院長自身の「心境」と「経営リソース活用のバランス」を次のような観点からチェックしてみてください。
スタッフ数のキャパを超えた患者数を求めていませんか?
院長は志も能力も高いのですが、スタッフにも同じような動きを期待してしまいがちです。
しかし経営者と従業員は能力も立場も違う事を念頭に置いて、戦力相応の仕事をさせるという考え方をとることが大切です。なぜなら、無理は長く続かないためどこかにしわ寄せが必ず来るからです。
医院が小さく、院長とのコミュニケーションが密に取れている段階であれば、細かい指示出しをしたり、動機づけを行うことでスタッフのパフォーマンスを上げることは可能ですが、10人~20人規模の組織運営の場合には、合理的な基準を設けて経営リソースの投資判断を行うことが大切です。
それが、長く安定した運営体制をつくり、採用、教育、労務のコスト削減につながるとともに、習熟したスタッフの生産性が上がるため、結果的に経済合理性も高くなることにつながります。
医院や院長のサポートは足りていますか?

勤務医の自費が少ない、診療人数が少ない、診療に時間がかかる、など嘆きたくなる時。
従業員がそれらの成果を上げるための教育サポートは足りていますか?
優秀な院長であるほど、スタッフにも同様のレベルを期待しがちです。
院長が「ツールをもらってきたからこの通り『初診コンサル』をやってね」と、ツールを渡せば、他の医院と同じようにスタッフが実践してくれる、という感覚で指示し、全く実装が進まないというケースを見たことは、1度や2度ではありません。
「見て覚えろ」や「自分で学べ」、で、成長できる人材も一部はいるでしょうが、大きな成功を目指していくのであれば、医院としてコンスタントに人が育つためのサポートやコミュニケーションの仕組みを整備することが重要です。
チーフや幹部に能力以上のことを期待していませんか?

院長の代理として、チーフや幹部にスタッフマネジメントの一部を権限移譲する場合、その役職に期待される仕事に比して、本人の能力が不足していると、組織内に不協和音・雑音(トラブル)が起きてきます。
・チーフや幹部がいつも遅くまで残業している
・チーフや幹部が休日も仕事でいっぱいになっている
・スタッフがチーフや管理職になりたがらない
こうした医院は運用を見直すことが必要です。人材の能力に応じて、仕事を配分する、必要な教育をするなど院長の適切なサポートが必要です。
経営者である院長は、常に成長と発展を目指しつつも、望む成果に見合った「投資」や「教育」、「時間を待つこと」など合理的な観点から判断をし、手を打つことが必要です。
「すぐに成果が出る手法」を探していませんか?

歯科医院経営は成長の壁の連続です。
一つ新しい「考え方」と「やり方」を発見し実践することで、事業が前進すると、すぐに次の壁が表れます。
このように歩みの遅さに焦りが生じると、
「なんか、いい方法ないかな~。」
「業績がグッとよくなる手法はないかな~」
「いい人材採用できるうまい手はないかな~」
など、「すぐに結果の出る手法」を探してしまうという思考法に陥りがちです。
それに呼応するかのように、SNSやWEB広告を見ると、
「〇千万円の収入を稼ぐTOP〇%の歯科医師が使っている〇〇を大公開」
「プロフィールだけで売り上げが〇倍になる秘訣」
「自費〇〇を毎月〇本出すセミナー」
等、すぐに結果が出るという手法やノウハウを訴求したPR広告がいくつも見つかります。
いつからか「ダイレクトレスポンスマーケティング」が流行したことで、「マーケティング手法で経営がうまくいく」という風潮が広がったように感じます。
「勝つべくして勝つ」合理的な経営努力を
もちろん専門家によるノウハウや、実績のある手法があり、これらを活用することはとても有効です。
しかし、「何かの手法を取り入れればうまくいく。」という手法中心の発想で、大事な観点を見失っていることがないでしょうか?
それは「勝つべくして勝つ」「成功すべくして成功する」という「合理的な経営努力」という観点です。
簡単な例を挙げると、
・プレゼンやトークのノウハウを取り入れれば「自費が増える」
・SEOやPPC、スマホサイトに投資すれば「患者が増える」
・ITツールでシステム化すれば「効率が上がる」
これらのノウハウや手法、ツールは有効ですが、それを取り入れただけで得られる成果にはすぐに限界が訪れます。
『質』の向上は手法だけでは実現できない
それはなぜでしょうか?
ひとつには、「経営にはバランスが重要」という観点が挙げられます。
中身が伴わないPR力はマイナスを生むことさえあります。
そしてもう一つは、
「『量』は偶然増えることはあるが、『質』の向上は地道な努力によってしか実現できない」という観点です。
長期にわたり安定的に成功していくためには、
「技術の向上」
「設備の革新」
「スタッフ教育」
「清潔や安全の環境整備」
「意志の疎通やチームワーク向上」
そしてそれらの経営資源を活かす立場にある「院長のマネジメント力」など、歯科医院に期待される当たり前のことを、常にレベルアップし続けるという、全うな努力の積み重ねでしか実現できません。
こうした本道を時より思い出し、経営者として「自分」と「医院」に投資を続けていくことが大切なのではないでしょうか。
「量は一過性の偶然があるが、『質』に偶然はない。『質』は努力や投資の積み重ねであり、偶然に質が良くなったということはありえない」。
地道な努力による「勝つべくして勝つ」道を忘れずに歩んでいきたいものです。
まとめ
このコラムでは、歯科医院を成長させていく際に、経営者である院長が押さえるべき思考法として2つのポイントをご紹介してきました。
- 「クレーム・トラブル・雑音」は見直しのシグナル
- 「勝つべくして勝つ」合理的な経営努力を
人生の法則や深い経営哲学を学ぶ源泉として、稲盛和夫氏のように仏教を学ぶ経営者も数多くいます。
この仏教の中核には「因果の理法(原因結果の法則)」という教えがあります。この因果の理法とは、「良き種を撒けば良き結果が実る。悪しき種を撒けば悪しき結果が実る。」という教えであり、「因果はくらますことができない」と指摘されています。
事業の成長を目指し、事業の目的を達成するためには、それに相応しい努力を積み重ねること。時間、エネルギー、お金など望む結果に相応しい種を撒くことこそ、「勝つべくして勝つ」思考法とも言えるのではないでしょうか。
どのような種を撒くことが、望む結果を達成するために必要か?ということは、医院のフェーズや、院長のパーソナリティ、構成員の能力、医院戦略によってさまざまに違いが生じます。
こうした観点から、ともに「良き種は何かを考え」「良い種を撒く」パートナーとして「Mr.歯科事務長サービス:経営参謀プラン」でお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。
みなさまの歯科医院経営のますますの繁栄をお祈りしております。
この記事の解説者

MOCAL株式会社 代表取締役
今野 賢二 Kenji Konno
歯科業界歴25年。歯科医院向けソフト開発・販売のベンチャー企業で、マーケティング・営業マネージャーとして、販売の仕組みづくりの中心的役割を担い、トップブランド構築に貢献。