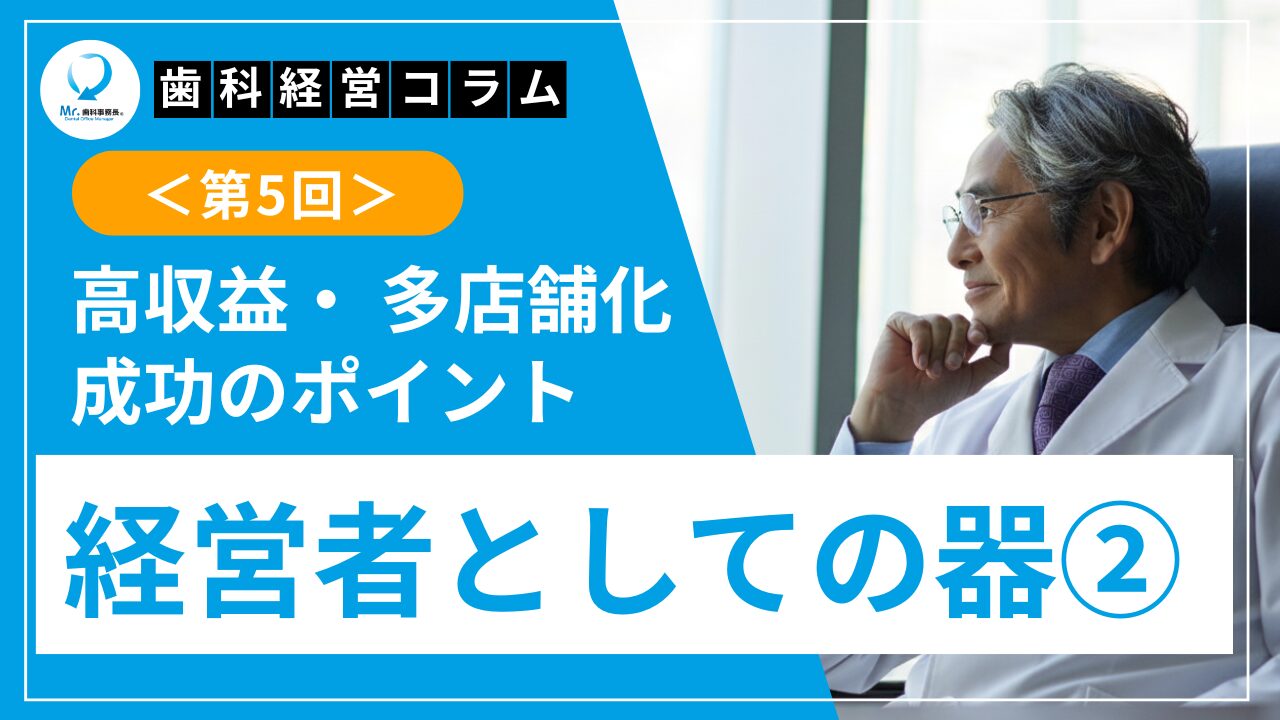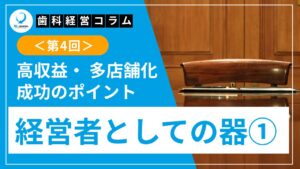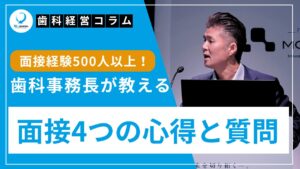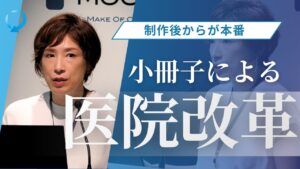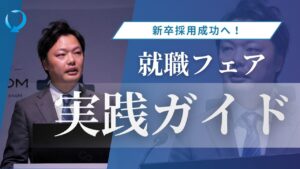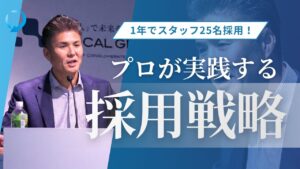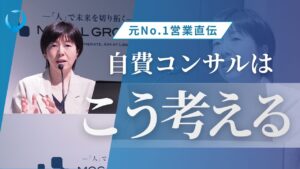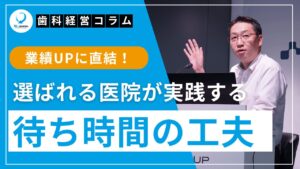このコラムでは「大型化・多店舗化に成功する歯科経営のポイントとは?」と題し5回に分けて情報をお届けしていきます。
今回は「経営者としての器づくり②」と題して、特に組織を率いるリーダーに求められる機能に焦点を当てて考えていきます。
経営とは「人を使って成果を上げること」という定義をされることがあります。その意味で、組織の長である院長は「人を活かす」「組織を動かす」という人事的な力が必要とされます。
今回のコラムでは、事業組織を率いる院長が押さえておくべき「トップとしての器/経営者としての器」として前回に引き続き、重要と思われる論点について考えていきます。
経営者には「教育者」の一面が必要

前述の通り、経営とは「人を使って成果を上げること」と定義されることがあります。
また「人は石垣、人は城」という武田信玄の有名な言葉もありますが、組織が大きくなればなるほど、トップは自分の理想や目標を「人事」によって実現していくという面があります。
さらに、ドラッカーは「人は無限に成長する資源である」と指摘しています。
これらの言葉から、経営者のもっとも重要な仕事は「人材の養成」であると言えるではないでしょうか。
実際に大規模化を実現しつつも「高収益体質」「トップ不在でも現場が回る」医院の多くでは、院長(理事長)が自ら教育に時間をかけ、また教育投資も惜しまずにされています。
ある一定規模まではきたが、収益力が落ちてきた、自分だけが忙しい、いつまで経ってもプレイヤーの一人から抜けられない、という方は「自分が目指す状態を実現するために必要十分な教育投資をしているか?」という観点からチェックされてみてはいかがでしょうか。
多様な人材を活かしチームを形成できるか

組織の形成過程は「分業」の過程でもあります。
開業当初は、院長もスタッフも1人3役など、幅広い業務を行ってきた方が多いのではないでしょうか。
しかし、患者数、スタッフ数が増えるに応じ「受付」「助手」「TC」の専任化など分業が始まっていきます。
次に、チーフなど中間管理職が誕生する一方、新卒採用をするなど、縦の階層も広がってきます。
さらに規模が大きくなると、事務方との分業、事務の中でも、経理、人事、マーケティング、ITなど、さまざまな役割を持った専門家が増えてきます。
組織が大きくなり、分業化、階層化が進むということは、それだけ「人間の種類(個性)」が増えることであり、その人間間・業務間の「摩擦」が生じてくることでもあります。特に優秀な人材ほど個性が強く、個性と個性がぶつかり合うという状況が頻発してきます。
第2回、第3回のコラムでは、これらの摩擦を組織的に解決するための方策や考え方について、紹介してきましたが「人間は感情の生き物」という測面があり、「ルール」や「規定」によるマネジメントだけでは十分に機能しません。
これは歴史の常でもあり、これらをどう統治(マネジメント)していくか?という探究から数多くの「帝王学」が生まれてきたと言えるでしょう。
では、多様な人材を活かしてチームを形成するために必要な人事の要諦とはなんでしょうか。
適材適所
その中心となるのが「適材適所」という言葉です。
ジャックウェルチは「適材適所というのは、戦略を立てることよりはるかに重要だ」と語っています。
また「経営者は人事を通じて自分の目指すものを実現する」という言葉もある通り、とても奥が深く、ある意味で経営者能力がこの1点で測られると言っても過言ではありません。
人物眼を磨く
まず、この「適材適所」ができる前提の一つが「人物が観える」ということであると言われています。
この人材の本質が観える。求めていることが観える。長所や短所が観える。能力やポテンシャルが観える。どこまで信用を与えられるか。どこまでの権限を与えてよいか。どういうところでつまずくか。
こうした人物眼が適材適所の成否を分けていくと言えるでしょう。
人事の基本は長所を活かす
次に、人事の基本は「長所を活かす」ことと言われています。
弱みに基づく人事ではなく、強みに基づく人事が基本です。
臨床力は高いがコミュニケーションが苦手。
臨床力は高くないが、後輩の面倒見がよい。
コミュニケーション力は低いが仕事が正確。
こうした長所・短所の両面を持つ人材を、どう活かすことが全体の成果につながるか?
さらに「人の組み合わせ」を考えるという視点です。
目標達成に邁進するが、部下とのコミュニケーションで摩擦を起こすタイプには、補佐役として潤滑油的な人をつける。
対外交渉や営業力が強いが、詰めが甘いタイプには、手堅く事務能力の高い補佐をつける。など、組み合わせで人事を考える視点が重要です。
組織を「調和させる力」
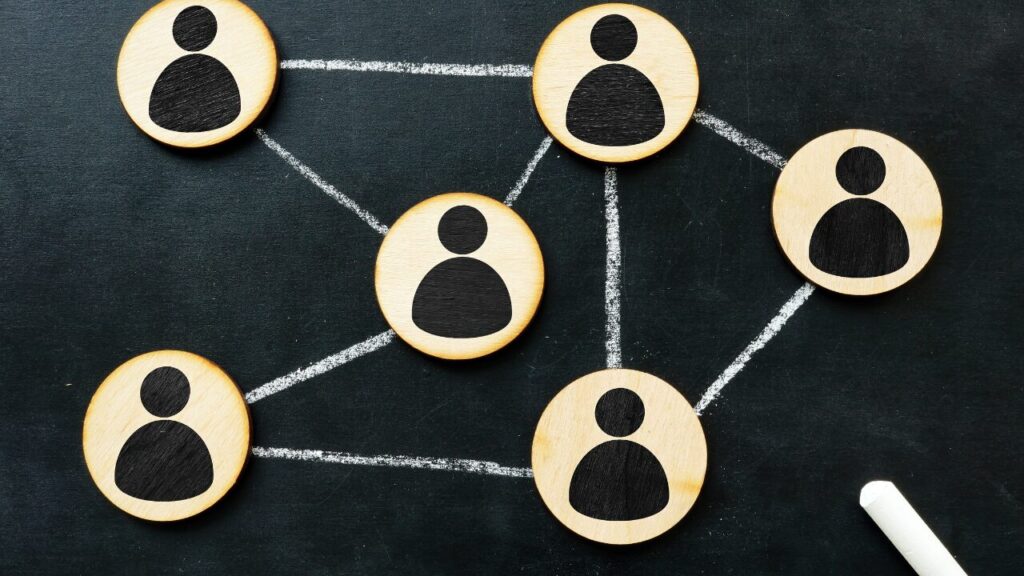
ここまでは、ある程度の「見識」や「能力」で一定の成果を生むことができる範囲です。
しかし組織が大きくなると強い個性を持つもの同士を「調和させる力」が必要になってきます。ここが本当の意味での「経営者の器」を考えるポイントになってくると考えられます。
この個性が強いもの同士を調和させることが難しい理由の一つは「経営者からは、その担当者の素晴らしい強みと見えていても、もう一方の担当者からは強みに見えない(理解できない)」という点が一つ。
もう一つは「嫉妬の原理が働く」という点です。
これをどう調和させるかということは非常に難しい課題であり、私自身も手探りでチャレンジしている過程ですが、以下に指針を紹介します。
人材を愛する器
一つは「人材を愛する」という視点です。
「士は己を知る者の為に死す」という言葉あります。また「愛するとは理解することである」、「理解するとは、相手の尊さを知ることである」とも言われています。
この意味で、数多くの「人間学」を学び、理解できる幅を広げ続けることが、組織拡大を目指す者の努力の方向性であると考えられます。
「どこまで組織を大きくできるかは、どれだけの人間を理解できるか」と指摘する識者もいます。
また「自分自身の中に発見した良きものしか、相手の中に発見できない」とも言われています。
この意味で、自分自身を深く耕す、内省的な経験も器づくりには不可欠と言えそうです。
こうした努力を上司(経営者)が続けていくことで、「自分を理解してもらっている」「自分を価値ある存在と思ってもらっている」という感覚を持ってもらえることができるのではないかと思います。
ある経営者の人事についての言葉に「欠点さえもかわいく見えてきた時に、本当に成功の道に入ってくる」というものがありました。
どれだの多くの、どれだけ幅広い個性を理解し、長所を愛せるか。経営者の「愛の大きさ」が組織運営にも関わっていると言えるのではないでしょうか。
大義を立てる
そして二つ目は「大義」という視点です。
過去の歴史を紐解けば、大義のために生きてきた方々の素晴らしい事例が数多くあります。
「大義」に向かって奉仕するリーダーのもとには、同様に、小さな自己実現やエゴを後回しにして、協力してくれる存在があります。
程度の差はさまざまですが、「患者さんのため」「スタッフのため」「地域医療のため」「歯科業界のため」「国家のため」「時代のため」など、経営者の大義への真摯さに応じて、個の事情より大義を優先してくれる協力者が現れてくるものと思われます。
この大義が、組織内の嫉妬を中和し、同じ目的に向かって調和を生み出す力になるのではないでしょうか。
まとめ
このコラムでは5回にわたり「多店舗化」「大規模法人化」を目指していくポイントとして、実際に私が歯科運営サポートを通じて、重要と思われた論点を紹介してきました。
特に第4回、5回では「人事」や「経営者の器」について考えてみました。このコラムのテーマとしてお伝えしたかったことのひとつに「ノブレスオブリージュ」という考えがあります。
これは欧米社会の道徳観の一つで「身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務がある」という意味の言葉です。
経営者は自分の理想や夢を実現していくだけではなく、患者さん、スタッフ、業界、社会、国家など、公的な面でもプラスの貢献を意識していくことが重要であると、私は考えています。
ぜひ、歯科業界でも数多くの大成功者が誕生するとともに、その方の周りや社会に、幸福が増え、世の中が明るく希望に満ちることを期待するとともに、私たちも、より一層真摯に、皆様のサポートに尽力して参ります。
弊社では、院長のパートナーとして歯科医院の経営成功を支援する「Mr.歯科事務長」サービス、「事務局アウトソーシングサービス」を提供しています。
これまで様々な規模、取組内容の医院様を400軒以上サポートしてきました。ご興味のある方はお気軽にお問合せください。
みなさまの歯科医院経営のますますの繁栄をお祈りしております。
この記事の解説者

MOCAL株式会社 代表取締役
今野 賢二 Kenji Konno
歯科業界歴25年。歯科医院向けソフト開発・販売のベンチャー企業で、マーケティング・営業マネージャーとして、販売の仕組みづくりの中心的役割を担い、トップブランド構築に貢献。