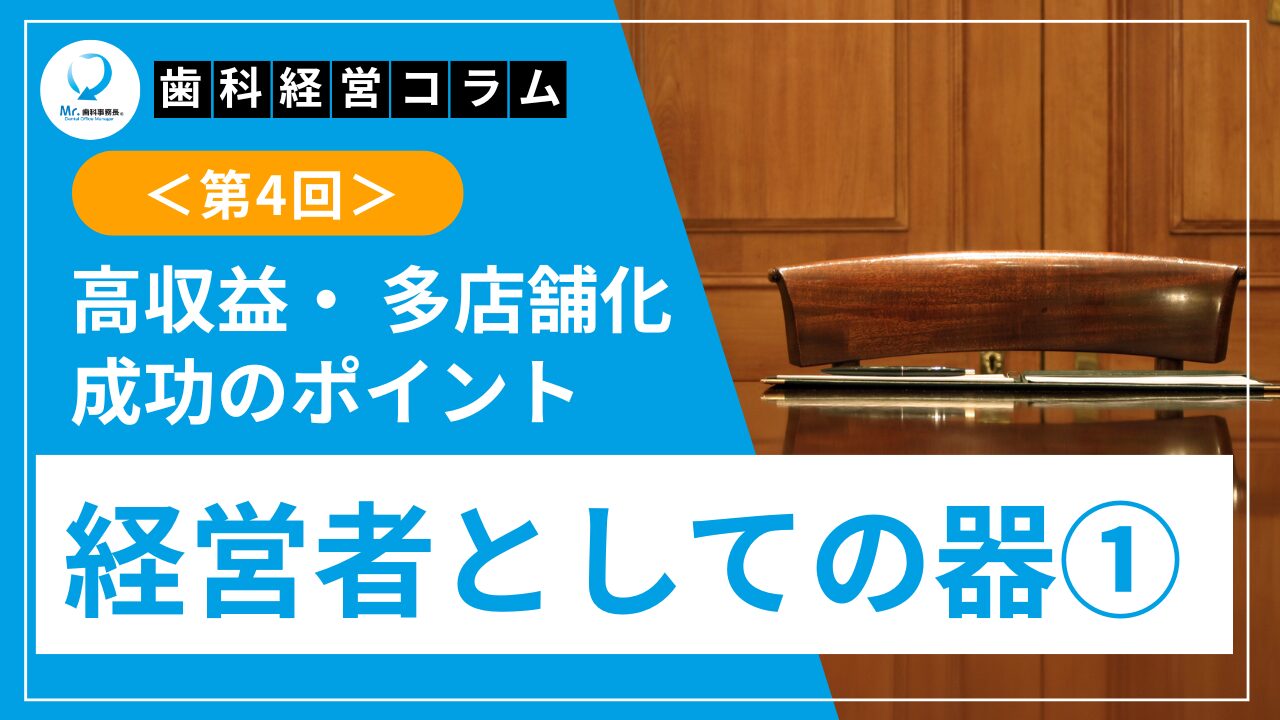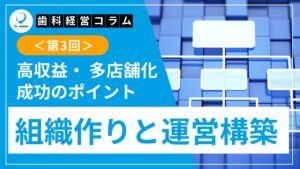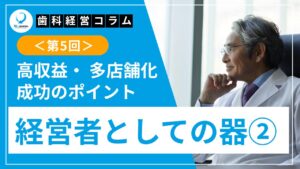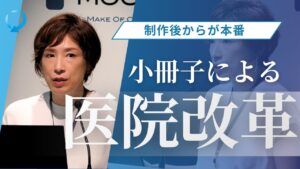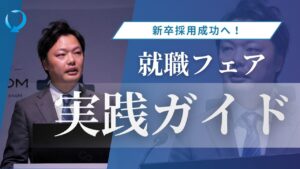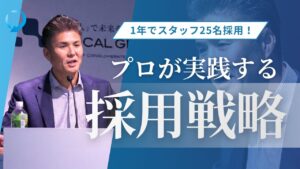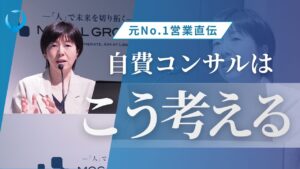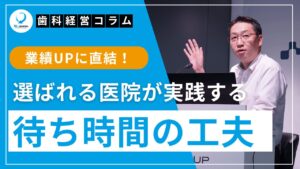このコラムでは「大型化・多店舗化に成功する歯科経営のポイントとは?」と題し5回に分けて情報をお届けしていきます。
今回は「経営者としての器づくり」と題して院長のリーダーシップに焦点を当てて考えていきます。
「経営の99%はトップ一人で決まる。」この言葉は、数多くの経営者や経営コンサルタントにより指摘されているため、一度は耳にしたことがあるという方は多いのではないでしょうか。
経営者にとっては、大変厳しい言葉であり、私自身も常に、自己変革や自己投資を心がける自戒の言葉としています。
今回のコラムでは、事業組織を率いる院長が押さえておくべき「トップとしての器/経営者としての器」としてどのような論点があるのか。基本となるポイントについて考えていきます。
「経営の99%はトップ一人で決まる」とは?

まず、なぜ経営の成果の99%はトップ一人で決まると言われているのか?その理由を考えていきましょう。
① 存在意義の定義「なぜ我々の事業が必要なのか~理念・ビジョン・価値観~」
事業や組織は一定の目的のもとに活動をしています。
どこに向かっているのか。何を実現しようとしているのか。
この組織で価値ありと称賛される基準は何なのか。
こうした根本的な方向性、存在意義を定義することはトップにしかできません。
② 意志決定
事業活動は「判断」や「意志決定」の連続です。
臨床的な診断や日常業務の現場判断は、現場スタッフにも一定の権限を与えることはあっても、事業における戦略上の判断、投資判断、価格設定、人事判断、品質基準の判断など、経営の根幹に関わる「意志決定」はトップ一人の責任の下に行われます。
③ リーダーの器~どれだけの人を活かせるか~
事業を構成する要素は、さまざまですが、結局は「その経営者についていきたい」と協力者が思えるか、という人間の感情面を無視することはできません。
何人の人を活かせるのか?使えるのか?リーダーの「人間としての器」が組織規模を決めると言われています。
こうした観点が「経営の99%はトップ一人で決まる」所以であると言えそうです。
この前提に基づき、大規模化を目指す歯科経営者にとって、私が現場の院長や理事長と接している際に、特に重要と考える「経営者の器」について記述していきたいと思います。
「決断力」~投資判断が早い~
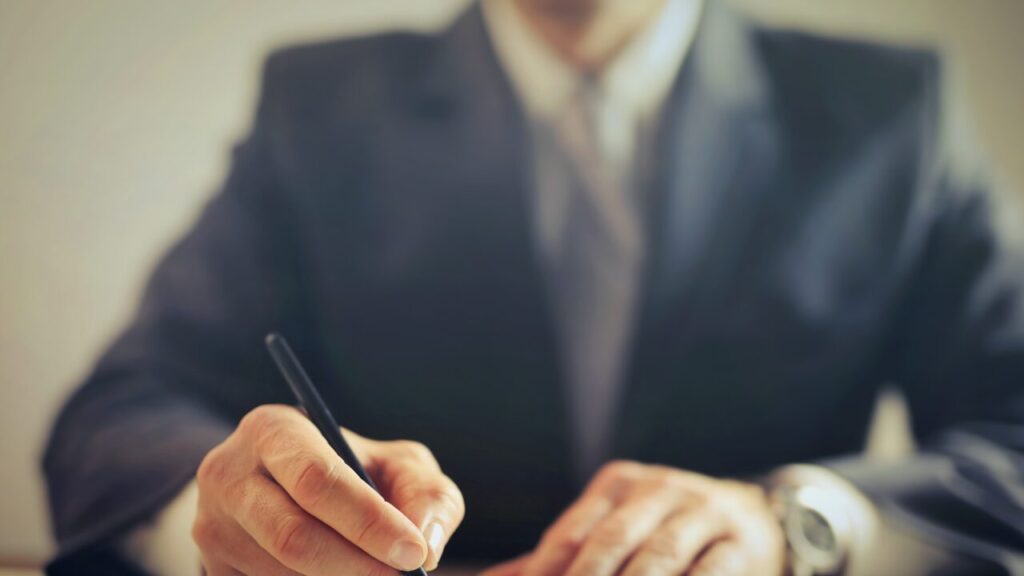
まず一つ目の「経営者の器」として「決断力(意志決定)」があげられます。
当然のことではありますが、事業の成長のためには「先行投資」が必要です。
これまで多店舗化、大規模化されている院長(理事長)と数多くお会いしてきましたが、例外なく、リスクをとって投資を行う「意志決定」が早いのが特徴の一つです。
敢えて強調したいのは「投資」が先ということです。その意味で投資には常にリスクがあります。
このリスクに対して、恐怖心や不安で意志決定をペンディングするのではなく、理性的にリスク分析をし、決断できる方が規模の拡大を実現しています。
逆に言えば、事業を大きくできない経営者の特徴は「リスクをとった投資をしない」と言えます。
ここ数年、事業規模に変化がない、と感じる方は、リスクをとった投資をしているか?という観点からチェックをしてみてはいかがでしょうか。
「医療」と「お金」の哲学
「経営者の器」として二つ目にあげたい論点は「医療とお金をつなぐ哲学」についてです。
医療に惹かれて職に就く方には、「利益」や「お金」に対して肯定的な感情を持っていないケースが非常に多いと言えます。
昔から「医は仁術」という言葉もあるように、医療は奉仕であるというイメージが根付いていることがその理由と考えられます。
しかしながら、ドラッカーは次のように指摘しています。
「どんな天使が経営をしたとしても、利益の概念は無視できない」なぜなら、利益とは「事業を維持・発展させていくためのコスト」であり、本当は「利益なるものは存在しない」。
事業を継続、発展させていくためには、スタッフの採用や教育、昇給、新しい臨床メニューや設備の導入、戦略的なリニューアルなどの様々なコストが発生します。
それらのコストを賄うための利益はどうしても必要です。
経営者である院長(理事長)にとって当たり前のことではありますが、組織全体に浸透させていかなければ強い事業構造、財務体質を実現させるのは難しいと言えるでしょう。
この意味で、医療を通じて「利益」を生み出すことを肯定していく「哲学(もちろん社会正義に基いた考え方)」「医療の使命とお金が矛盾なく融合するマインド」を、トップが明確に言葉にし、構成員に説得的に浸透させていけるかどうかが、事業拡大を目指すうえで必須の要件の一つであると考えます。
ここが曖昧である場合は、強い事業構造(院長のスーパーパワーで売上をつくるのではなく、組織として収益力を高める)をつくることは困難です。
また、院長自身の哲学が社会正義に基づいていない場合には、
- 着服などの不正が起きる
- 職場のモラルが低い
- スタッフ同士の仲が悪い
- スタッフが役職につきたがらない
- 離職率が高くなる
など、組織運営に歪みが出てくることがあります。
自分の成功はスタッフの幸福につながるか

三つ目の論点は、院長の事業成功に対する「哲学」についてです。
スタッフ数が多くなり、「個人経営」から「事業経営」に脱皮していくためには、数多くの協力者が必要です。
開業当初は、院長の診療を補助する「作業補助者」としての役割をスタッフに期待しているケースが大半と思われますが、事業成長に伴い、スタッフを「作業補助者」から「協力者」に変えていく必要があります。
この際に、変えるべきポイントは、スタッフではなく、院長自身の「成功哲学」にあります。
「スタッフは自分自身の成功のための補助者である」という考え方から、「院長自身の成功が、スタッフや患者さんの幸福につながる」という「成功哲学」にシフトしていくことが大切になります。
これは仏教の「利自即利他」の思想に通じます(自分を利することが、即、他人を利するという共生の考え方)。
弊社では、成功している院長へのインタビューを収録した「院長の経営成功術(CD)」を発刊しています。
このインタビューでも、複数の院長が、この「成功哲学」へのシフト(表現はそれぞれ違いますが)を指摘されています。
スタッフが、院長の成功のために、熱心に働いてくれることはありません。
院長が示す理念や目標達成を通じて「患者さんに喜んでもらえる、やりがいを感じられる、成長が実感できる、生活がよくなる」など、医院の成功と自身の願いの一致があって、初めて協力者として熱心に働いてくれるようになります。
とてもシンプルな論点ですが、「自分だけの成功」を考えている場合は、誰も真摯に協力してくれませんが、「患者さんやスタッフの幸福」も同時に考えていくことで、協力者が増えていきます。
院長が私たちをどの程度大切に考えてくれているのか?
「院長の本音」をスタッフは実に正確に、匂いとして嗅ぎ分けています。
とても厳しいことではありますが、「経営者の器」として、こうした哲学や考え方、マインドを自分自身の中に醸成していくことが、多くの従業員を率いていくリーダーに期待されているのではないでしょうか。
まとめ
このコラムでは、大規模化・多店舗化に成功する歯科医院経営のポイントについて「経営者の器」の観点からご紹介してきました。
「事業は人なり」という言葉がありますが、まずはトップである院長(経営者)自身の器の成長が、事業成長に直結するという捉え方が重要であると言えるのではないでしょうか。
次回のコラムでは、「経営者の器について考える②」と題して、「多様な人材を活かす」「長く成功を持続させる」ための経営者の器について考えていきたいと思います。
みなさまの歯科医院経営のますますの繁栄をお祈りしております。
この記事の解説者

MOCAL株式会社 代表取締役
今野 賢二 Kenji Konno
歯科業界歴25年。歯科医院向けソフト開発・販売のベンチャー企業で、マーケティング・営業マネージャーとして、販売の仕組みづくりの中心的役割を担い、トップブランド構築に貢献。