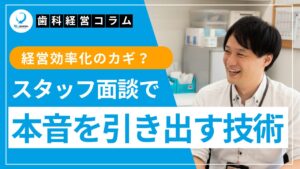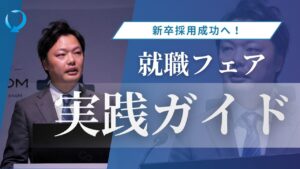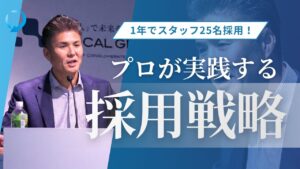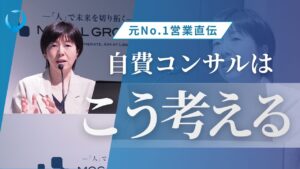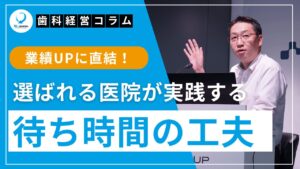「毎月の売上がなかなか伸びない」 「スタッフの教育がうまくいかない」 「新しい施策を試しても、持続的な成長に繋がらない」
多くの歯科医院経営者が、こうした悩みを抱えています。 実は、着実に成長を続ける歯科医院には、派手な経営テクニックではなく、強固な「土台」が存在するという共通点があります。この土台がしっかりしているからこそ、どんな状況でも安定して成長し続けることができるのです。
この記事では、売上を伸ばし続ける歯科医院に共通する5つの「土台」について、具体的な事例を交えながら解説します。自院の現状と照らし合わせながら、ぜひ最後までお読みください。
スタッフの教育が「仕組み化」されている

なぜ「教育の仕組み化」が売上に繋がるのか? これは経験の有無にかかわらず、新人スタッフが最低限の標準レベルに早く到達できるようになるためです。結果として、教育にかかるコストと時間が削減され、新人がより早く医院の収益に貢献できるようになります。
何より、院長や先輩スタッフが教育に割く「貴重な時間」を大幅に削減できるメリットは計り知れません。 院長の時間は、医院にとって最も価値のある資産です。院長が1時間診療すれば100万円の価値を生み出せたかもしれない時間を、仕組み化できるはずの教育に費やすことは、経営上の大きな機会損失です。
教育の仕組み化は、この「見えないコスト」を削減し、医院の収益性を直接的に高めるための必須条件と言えるでしょう。
仕組み化で重要なのは単に「やり方」を教えるだけでなく、各業務の「なぜ、それを行うのか」を明確にすることです。 このプロセスは、習慣で続けられてきただけの非効率な業務、つまり「形骸化してしまった価値のない業務」を洗い出し、排除する絶好の機会にもなります。
ある医院では、滅菌や片付けの流れを見直したところ、スタッフそれぞれが少しずつ違う手順で、中には非効率なやり方をしている人がいることが判明しました。 そこで、最も効率的な手順を全員で洗い出して文書化(マニュアル化)し、それを標準ルールとしました。その結果、以降に入職したスタッフは誰に教わっても同じ手順をスムーズに覚えられるようになり、教育が格段に楽になったという事例があります。
院長がスタッフの「主体性」を重視している

多くの院長が陥りがちな間違いは、スタッフからの提案に対して「いや、それは違うな」「過去にやったけど意味がなかったよ」と、即座に否定してしまうことです。 これではスタッフの「次も提案しよう」という意欲を削いでしまいます。
主体性を育てる「承認」と「誘導」 成功している院長は、コミュニケーションに工夫を加えています。
1.まず、提案してくれたこと自体を「すごくそのアイデアいいね」と肯定的に受け止めます(承認)。
2.その上で、「そのアイデアを活かしつつ、もう少しこう加えてみるのはどう思う?」と、院長の意図する方向に導きながらも、相手の意見を取り入れる形で対話を進めます(誘導)。
このような関わり方を続けることで、スタッフは「自分の意見が認められた」と感じ、主体性が育っていきます。 長期的には、院長が不在でもスタッフが主体的に動けるチームが育ちます。これは、「院長がいないと医院が機能停止する」という最大のリスクを回避することにも繋がります。 結果、院長は目先の業務から解放され、より重要な経営判断に時間を使えるようになり、医院のさらなる成長へと繋がるのです。
心理的安全性が高く、感謝を伝え合える

心理的安全性が高い職場とは、スタッフが「ここに自分の居場所がある」と感じられ、意見を言ったり失敗したりしても、誰もそれを責めない環境のことです。 給与は高いのに、この安全性が確保されていないために離職者が後を絶たない、というクリニックは少なくありません。
スタッフが定着し長く働き続けてくれること自体が、医院にとって最大の利益となります。新たな採用コストや教育コストが発生しないことは、経営における最強の「資産防衛」と言えます。
心理的安全性を高める「共通体験」 では、成功している院長はどのようにしてこの文化を築いているのでしょうか。 その一つが、社員旅行やレクリエーション、あるいは一緒にセミナーに参加するなど、「共通の体験をする場」を積極的に設けることです。
これらは単なる娯楽ではなく、チームとしての連帯感を育むための重要な「投資」です。「若いスタッフは嫌がるかもしれない」という院長の思い込みからこれらの機会を過剰に排除しすぎるのは、非常にもったいないことです。 共に何かを体験することで共通の話題が増え、お互いの人となりを知り、心を開いてコミュニケーションが取れるようになるのです。
全員が「患者満足度」を本質で理解している
「接遇」と「患者満足度」の違い これは単に綺麗な丁寧語を使うといったテクニカルな「接遇」を指すのではありません。 たとえ言葉遣いは完璧でも、冷たい声のトーンや、面倒そうな態度で話されては、患者さんが心から満足することはないでしょう。患者さんが本当に心地よいと感じ、「またこの医院に来たい」と思えるような体験を提供することが本質です。
実際に、インターネットの悪い口コミを見てみると、治療内容そのものよりも、受付の対応や電話応対といった、スタッフの「態度」に対する不満が非常に多く見られます。
患者満足度を「仕組み化」する 患者満足度を向上させるための具体的な戦略として、ある医院では以下の取り組みを実践しました。
- 定期的な患者アンケートを実施してフィードバックを収集する。
- 良かった点、悪かった点の両方をスタッフ全員で共有する。
- 良かった点は「自分たちの強み」として維持・強化する。
- 悪かった点は「次のアンケートまでに全員で改善すべき最重要課題」として意識を統一する。
この取り組みによって、チーム全体の改善努力の方向性が明確になり、結果として満足度が向上。リピート率やメンテナンス継続率の上昇、さらには紹介患者の増加といったポジティブな成果に繋がりました。
医院の「経営理念」を全員が理解し、共感している
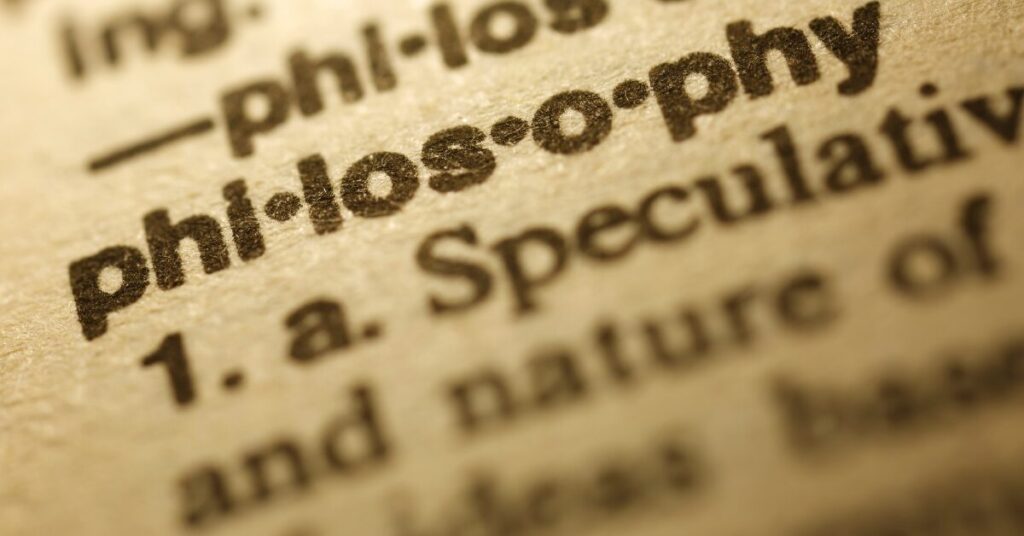
経営理念とは、そのクリニックが「何のために存在するのか(存在意義)」を定義するものであり、数ある歯科医院の中から患者さんや求職者に選ばれるための重要な差別化要素となります。
理念がスタッフ全員に浸透する最大のメリットは、全員の「判断軸」が揃うことです。 「私たちの医院が目指す姿はこうだから、この場合はこう行動すべきだ」という共通認識が生まれるため、判断のブレがなくなり、院長のビジョンに沿った一貫性のある医院運営が可能になります。
ある院長は、理念を策定する過程で、まず自分自身の向かうべき方向が明確になったと言います。「自分が本当にやりたかったのは、患者さんが再発せず健康でいられるための予防治療だ」という情熱を再確認したのです。 この明確なビジョンがスタッフにも伝わり、医院全体が活性化。数ヶ月先まで予約が埋まるほどメンテナンスの希望者が殺到するクリニックへと変貌を遂げました。
ここで最も重要なのは院長自身が理念に反した行動を絶対に取らないことです。「理念ではこう言ってるけど、それはそれ、これはこれ」という態度を取った瞬間、理念はただのお題目となり、意味を失ってしまいます。
さらに、明確で共感できる理念は、採用活動にも絶大な効果を発揮します。「この理念を一緒に実現したい」と考える、価値観の合った人材が自然と集まりやすくなるのです。
まとめ
今回ご紹介した5つの共通点は小手先のテクニックではなく、医院の文化として根付かせるべき長期的な成長の「土台」です。 これらが強固であればあるほど、クリニックは外部環境の変化に左右されず、持続的に成長し続けることができます。
あなたの医院の「土台」は、どれくらい強固ですか? ぜひこの機会に、一つひとつ見直してみてはいかがでしょうか。
この記事の解説者

この記事の解説者
Mr.歯科事務長
信田 学 Manabu Nobuta
神奈川県出身 血液型O型
大学在学中、インディーズレーベルよりCDデビューを果たし、音楽活動によるボランティアや多くの人々とのコミュニケーションを通じ実社会の厳しさや人の暖かさを実感する機会にも恵まれました。
一部上場企業での勤務や、ITベンチャー企業での分社立上げ・運営を経験後、歯科医院向けコンピューターシステムのコンサルティング営業に従事し、日本全国の数百歯科医院を担当。No1営業の達成経験やマネージャー経験を活かし、より深く医院の成功実現に寄与したいとの想いからMOCALに転職を決意!
休日は一児の父、2匹の猫親として日々奮闘中。色々な役割の中で、学びを得て成長しています。