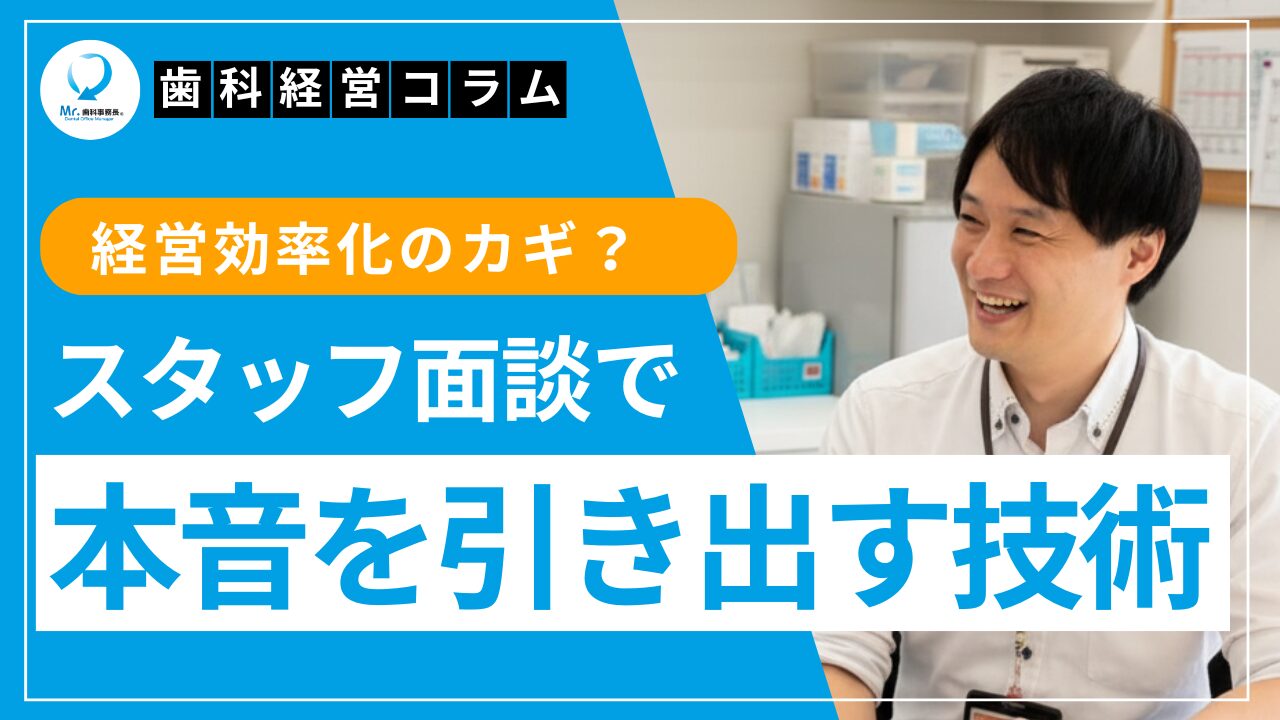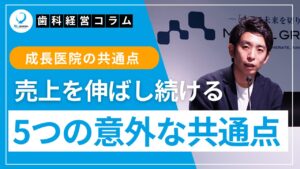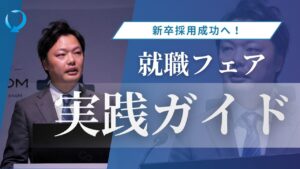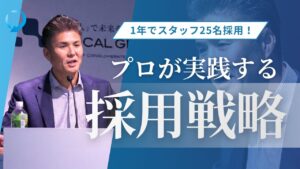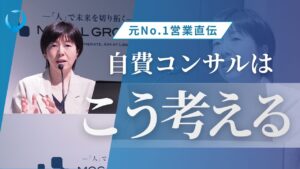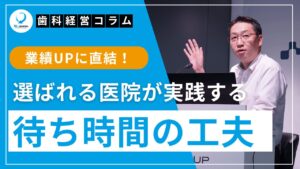「面談」を経営効率化のヒントに
院長にとってスタッフ面談は、「評価」や「面倒な業務」になっていないでしょうか。しかし、日々の面談こそが「医院のムダをなくす=経営効率化」の最大のヒントが眠る宝の山です。特別な手法は不要です。普段の対話の中にこそ、人・モノ・時間の「もったいない」や、医院の流れを滞らせる「つまずき」の兆候が隠れています。
このコラムでは、面談から見えてきた「経営効率化」のコツを具体的にご紹介します。

なぜ歯科医院こそ「面談」が経営効率化に効くのか?
どうして、スタッフ面談はそれほど重要なのでしょうか。それは歯科医院特有の構造にあります。
1. 院長が「プレイングマネージャー」であること
院長はトップの臨床家であると同時に経営者です。日中は診療に集中するため、医院全体を俯瞰して見ることが物理的に困難です。 「受付のAさんと衛生士のBさんの連携がうまくいっていない」 「バックヤードの在庫管理が非効率なまま放置されている」 こうした「診療室の外」で起きているムダや非効率は、院長の目には届きにくいのです。面談は、院長が直接見ることができない「現場の生の声」を吸い上げる唯一の公式な場となります。
2.職種間の「見えない壁」があること
歯科医師、衛生士、助手、受付…。専門職が集まる歯科医院では、職種間のセクショナリズム(縄張り意識)が生まれやすい傾向があります。 面談はこうした「見えない壁」を超えて、スタッフが「自分の持ち場」以外で感じている疑問や非効率(例:「衛生士として、受付の予約の取り方に疑問がある」「助手として、衛生士の準備の仕方にムダを感じる」)を吸い上げる、数少ない貴重な機会となります。
3.スタッフの「小さな不満」が経営リスクになること
「面談で話しても無駄」とスタッフが諦めている医院は危険信号です。 小さな不満は蓄積されると「業務の非効率」に直結します。例えば、「あの器具の場所が使いにくい」という不満を放置すれば、スタッフは毎回遠回りしてそれを取りに行くという「時間のムダ」が常態化します。 さらに、不満を持つスタッフは自発的な業務改善提案をしなくなるだけでなく、最低限の指示待ち業務しか行わなくなり、結果として医院全体の生産性が著しく低下します。面談は、この「不満の芽」を「業務改善のタネ」に変えるチャンスなのです。
面談は「伝えたつもり」を防ぐ最高の場

多くの院長が「スタッフコミュニケーションは大事だ」と理解しつつも、「何度も伝えたのに、全然伝わっていない」「いちいち言わなくても分かってほしい」というジレンマを抱えています。
あるデータでは、人に何かを伝えたとき、実際には相手に2~3割程度しか伝わっていないとも言われています。 院長が朝礼で「今月はキャンセル率を下げましょう」と伝えた「つもり」でも、スタッフには「また院長が何か言っている」程度にしか響いておらず、具体的な行動に繋がらないのです。
面談は、この「伝えたつもり」を「確実に伝わった」状態に変えるための絶好の機会です。 1対1の場で、「この前の朝礼で伝えたキャンセル率の件、Aさんはどう思う?」「何か良いアイデアないかな?」と問いかける。 そこで初めてスタッフは「自分事」として捉え、「実は、リマインドのタイミングが悪いのではと…」といった現場の具体的な意見が出てきます。
全体への指示では伝わらないことも、面談での対話(1対1)によって初めて血の通った施策になるのです。
日報を「報告」から「医院の資産」へ変える
ある医院では、「日報」は業務を終えて提出する「義務」でした。 面談で「その日報、何のために書いているんですか?」と尋ねると、「特に意味は…」「院長が見ているかも分からない」という声がほとんど。 つまり、「提出して終わり」「チェックしても活かせていない」という状態だったのです。これはスタッフのモチベーションを下げるだけでなく、「日報を書く」という時間そのものが「ムダ」になっていました。
そこで行ったのは、以下の2点です。
フォーマットの変更
単なる業務報告(何をしたか)だけでなく、「業務上の気づき」「困ったこと(課題)」「患者様からの嬉しい一言(成功体験)」を書ける欄を設けました。
「活かす場面」を強制的に作る
日報に目を通す責任者(院長や事務長)が、翌朝のミーティングで「昨日の日報にあった気づきを1つ共有します」という時間を設けました。
さらに、面談の際にはその日報を(できれば事前に目を通して)手元に置き、「この前の日報に書いてくれた〇〇の件だけど…」と具体的にフィードバックします。
日報というテキストコミュニケーションだけでは伝わらない「承認」の気持ちを、面談という対面コミュニケーションで補完するのです。 これにより、スタッフは「院長はちゃんと自分の日報を見てくれている」と実感し、日報は「単なる報告」から「院長との重要なコミュニケーションツール」、そして「医院の課題を可視化する資産」へと変わりました。
改善の流れを「作って終わり」にしない
面談をしていると、「それ、前にも同じこと話しましたよね?」という、諦めにも似た声が出ることがあります。 これは、「決めたはずの改善策が定着していない状態」の表れです。
多くの歯科医院が、新しいマニュアルの作成、新しいツールの導入など、「改善施策を決定し、実施する(Plan→Do)」ところまでは熱心に行います。 しかし、その後の「現場で本当に機能しているか?(Check)」「問題点はないか?(Action)」という検証が忘れ去られがちです。
私がある医院の面談でこの課題に直面した際、導入したのは非常にシンプルな仕組みです。
「変更点チェックリスト」の作成: 何がどう変わったのかを一覧化し、全員に配布・掲示する。
「フォローアップ面談(10分)」の実施: 変更後1~2週間後に、「新しいやり方、やってみてどう?」「困ってることない?」と、必ず感想を聞く時間を設けました。
この「フォローアップ面談」で重要なのは、院長が「具体的に聞く」ことです。 「どう?」と漠然と聞くのではなく、「具体的にどこがやりやすくなった?」「逆に、前より時間がかかるようになった業務はない?」「Aさんは使いこなしてるけど、Bさんは困ってない?」と深掘りして聞くことで、現場で起きている「小さな歪み」を早期に発見できます。
人はそれぞれ感じ方も考え方も違います。院長が「良かれ」と思って導入した改善策が、現場のスタッフにとっては「かえって非効率になった」と感じているケースは非常に多いのです。 この「認識のズレ」を調整する場として、面談は不可欠なのです。
「面談」が断ち切る「負のサイクル」
スタッフコミュニケーションが機能不全に陥った医院では、しばしば「負のサイクル」が発生します。
- スタッフがミスをする。
- 院長が(忙しさも相まって)強い口調で叱責する。「前に言っただろ!」
- スタッフは「怒られた…」「聞きづらい雰囲気だな…」と萎縮する。(院長の言葉そのものより、表情や声のトーンという非言語情報にダメージを受ける)
- スタッフは自信を失い、次のミスを恐れて「報告・連絡・相談」をしなくなる。
- 結果、小さなミスが隠蔽され、さらに大きなミスやクレームに発展する。
このサイクルに入ると、医院の経営効率は著しく低下します。 定期的な「面談」は、この負のサイクルを断ち切るための最も強力な装置です。
面談の場で、院長が「評価者」としてではなく、「支援者」として「最近困っていることはない?」と傾聴の姿勢を見せること。 そこでスタッフが「実は、〇〇でミスをしてしまいそうで怖いです」と勇気を出して課題を共有してくれたら、決して責めずに「話してくれてありがとう。どうすれば防げるか一緒に考えよう」と受け止めること。
この「心理的安全性(ここでは何を話しても大丈夫)」が担保された面談を繰り返すことで、スタッフは「聞きづらい雰囲気」を感じなくなり、日常業務においても「報連相」が活性化します。 ミスや課題が早期に共有されれば、それは「大きな問題」になる前に「改善のヒント」へと変わるのです。
「目の前の小さな工夫」に院長が気づけるか

面談の中で、一番ワクワクするのが「こんなふうにやってみたんですけど…」という、スタッフの自発的な「小さな工夫」に出会う瞬間です。
「アポイントが空いた時間で、器具のパッキング方法を見直してみました」 「患者さんの反応がよかったので、自費コンサルの説明資料の順番を少し変えてみました」
これらは院長が指示したわけではない、現場の「生きた知恵」であり、経営効率化に直結する非常に価値あるヒントです。 しかし、院長が「聞きづらい雰囲気」を出していると、スタッフはこれらの工夫を「報告するまでもないこと」として、発信してくれません。
面談は、この「埋もれた知恵」を発掘する絶好の機会です。 大切なのは、「聴く側」の姿勢です。 面談の際は、評価するのではなく「宝探し」をする感覚で、「最近、仕事で『ちょっと変えてみた』ことある?」と尋ねてみてください。
そして良い工夫を見つけたら、「その場で」「具体的に」褒め、ミーティングなどで「全員に共有」する。 「〇〇さんのあの工夫、素晴らしいから医院の正式なマニュアルに加えよう」とまで言えれば最高です。
院長からの「承認」という光を当てることで、スタッフの「小さな工夫」は「医院全体の資産」へと変わり、何よりスタッフ自身の「自分もこの医院を支える一員なんだ」というメンバーシップ(貢献意欲)を引き出します。
まとめ

面談とは評価のための時間ではなく、医院の未来をつくる「経営の一場面」です。 小さな声、小さなつまずき、小さな成功体験。 それらが医院の「ムダ」をなくし、経営効率を左右する大きなヒントになります。
「伝えたつもり」を防ぎ、スタッフの「本音」を傾聴すること。 「言いっぱなし」で終わらせず、改善策を一緒に調整すること。 「負のサイクル」を断ち切り、スタッフの「小さな工夫」を承認すること。
効率化は、高価なシステム導入やマニュアル作成の中だけにあるのではなく、日々の対話の中にあります。
面談を通して、そのスタッフがどんな経験を経て今があり、何を大切にしているのか(志向性)を知ること。 そして、その志向性に応じて「Aさんはコツコツ作業が得意だから在庫管理の仕組み化を」「Bさんは人と話すのが好きだから新人教育のメンターを」と役割を最適化(=適材適所)していくこと。 それこそが、スタッフのモチベーションと医院の業績を同時に高める、本質的なマネジメントです。
そんな想いを込めて、面談という「対話の場」を、ぜひ医院経営の力強い味方にしていってください。
もし、もっとスタッフとの関係づくりや、面談を起点とした医院の組織づくりについて深く考えてみたい先生がいれば、私たち「Mr.歯科事務長」がお手伝いできるかもしれません。 ご興味があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の解説者

MOCAL株式会社
菊池 一徳 Kazunori Kikuchi
専門学校卒業後、料理の勉強をするためフランスへ渡り、帰国後は代官山のフレンチレストランでサービスと調理に従事。
その後、カフェプロデュースを手がける会社で店長として店舗運営を経験した後、自ら法人を設立しカフェを創業。大田区のビブグルマン「OTAイチオシグルメ」で最優秀賞を受賞した他、不採算店舗の立て直しコンサルタントとしても活動。M&Aで会社株式を譲渡した後は、再びカフェプロデュースの会社に戻り、ジェネラルマネージャーとして活躍。現場でのホスピタリティやマネジメント、マーケティングの経験を活かして約200名のスタッフを管理し、採用や人事面談も多数実施した経験を持つ。
カフェ業界での経験を活かして、クリニックの課題に寄り添い、悩みや孤独を理解した上でサポートしたいという想いから、MOCAL株式会社に入社。