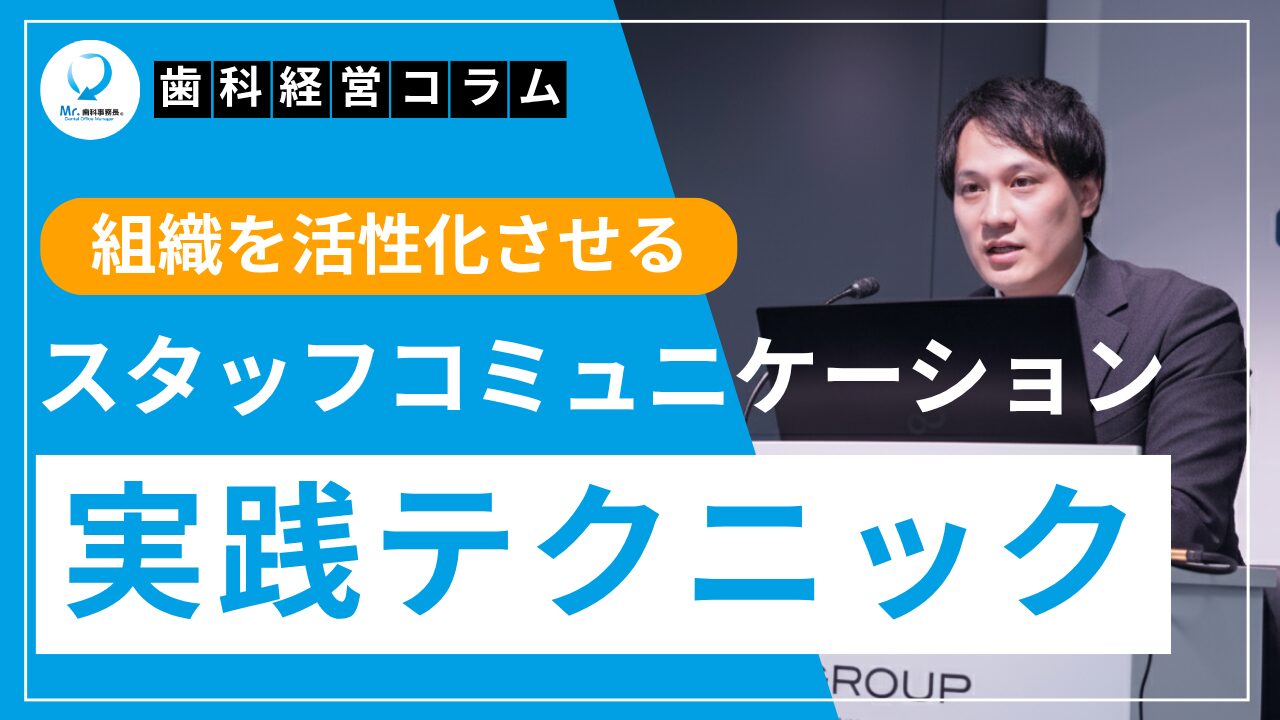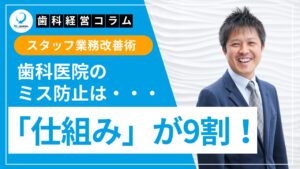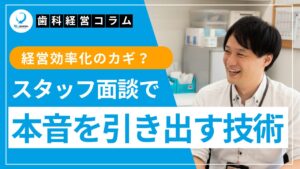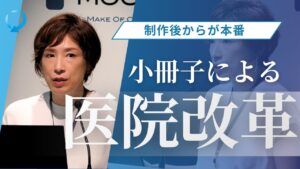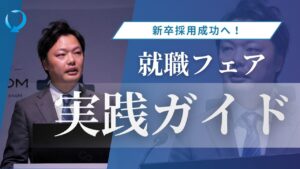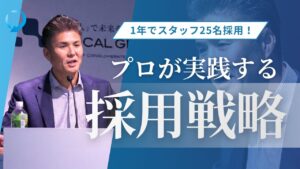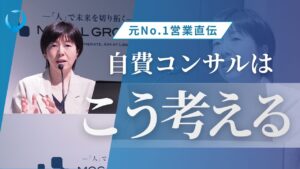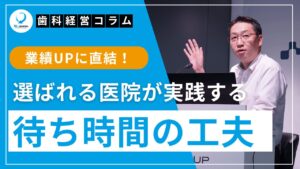歯科医院の経営と聞くと「数字」が先行してイメージされがちですが、経営の成功に最も重要な要素の一つが「人と環境(組織)のマネジメント」です。医院にとって「人」はお金と同様、もしくはそれ以上に重要な資産です。しかし、多くの医院がそのマネジメントに悩んでいます。
このコラムでは、特に「スタッフコミュニケーション」に焦点を当て、医院経営における組織づくりの考え方をお伝えします。
マネジメントに頭を悩ませる院長が多い理由

ドラッカーの言葉を借りると、マネジメントとは「組織が成果を上げるためのツール」です。歯科医院で言えば、院長の想いをスタッフが理解し、同じ目標に向かって患者さんにサービスを提供する環境を整え、改善を続ける仕組みのこと。それは「医院を良くするための設計図」そのものです。
特に歯科医院のマネジメントが難しいのは、院長自身がトッププレイヤー(臨床家)でありながら、同時に経営者・管理者(マネージャー)でなければならない点です。診療に集中したいのに、スタッフの悩みや労務問題にも対処しなければならない。この構造的な難しさが、多くの院長を悩ませる根本原因となっています。
医院全体の組織づくりの第一歩
院長先生が描く未来像(理念)をスタッフと共有し、同じゴールに向かう「土壌づくり」が、医院全体の環境づくりです。理念をただ壁に貼るだけでなく、日々の診療で「なぜそれを行うのか」を院長の言葉で伝え続けることが重要です。
一方で院長の指示が、「場当たり的」だったり、「本音を言えない雰囲気」の場合はスタッフが院長の顔色を伺ってしまい、業務改善の提案が出てこなかったりする状態になります。
日々の小さな情報共有や声かけ、心配りの積み重ねこそが、理念の浸透を促し、医院全体の安定感と強固なチーム力に繋がります。「クレド(行動指針)」を作成し、それをミーティングなどで読み合わせるなども、土壌づくりの有効な手段の一つです。
なぜ歯科医院ではコミュニケーションが難しいのか?

多くの院長が「スタッフとのコミュニケーションは大事だ」と頭では理解しています。しかし、歯科医院の現場では、なぜかコミュニケーションがうまくいかないケースが後を絶ちません。医院にはコミュニケーションを阻害する特有の要因があります。
院長のプレッシャーと多忙さ
院長は「経営者」と「臨床家」の二役を担い、常にプレッシャーに晒されています。診療が長引けば、スタッフへの指示が雑になったり、経営数字が悪ければ、無意識にピリピリした雰囲気を院内に撒き散らしてしまったりします。この「院長の余裕のなさ」が、スタッフが声をかける最大の障壁となります。
職種間の壁
歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、受付、技工士など、専門性が異なる職種が集まるため、「自分の仕事はここまで」という意識や、お互いの業務への理解不足からも壁が生まれがちです。 例えば、「受付は衛生士の忙しさが分かっていない」「衛生士は助手のサポートを当たり前だと思っている」といった小さな不満が蓄積し、連携ミスや対立に発展することは珍しくありません。
「言わなくてもわかる」という期待
院長は「これくらい察してほしい」「何度も言わせないでほしい」とベテランスタッフに期待しがちです。一方でスタッフ側は「今、院長は忙しそうだ」「こんな初歩的なことを聞いていいだろうか」と躊躇します。この双方の遠慮と期待が、最も重要な報告・連絡・相談(報連相)の機会を奪います。
「伝えたつもり」が引き起こすコミュニケーション不全

人は、自分が伝えた内容の2~3割程度しか相手に伝わっていない、というデータがあります。
そして歯科医院の現場では、「何を言ったか」という言葉(言語情報)以上に、院長先生の「声のトーン」や「不機嫌そうな表情」「腕組み」(非言語情報)をスタッフは敏感に感じ取ります。
よくある負のサイクル
- 院長が(忙しい時に質問され)「前に言ったよね?」とイライラした態度で指示を出す
- スタッフは「怒られた」「聞きづらい」と感じ、萎縮する。「忙しい時に話しかけてはいけない」と学習する
- 肝心な指示の内容が頭に入らず、疑問点も確認できないまま業務にあたる(あるいは、確認を諦める)
- 結果、ミスが再発する。もしくは、患者様に迷惑がかかる直前で別のスタッフがフォローする
- 院長は「なぜ同じミスを繰り返すんだ!」とさらに苛立つ
- スタッフは自信を失い、ミスを隠蔽したり、報告を遅らせたりするようになる
この「伝えたつもり」と「聞きづらい雰囲気」のサイクルが、歯科医院のスタッフコミュニケーションを決定的に悪化させ、組織の活力を奪っていきます。
コミュニケーション不足が招く医院経営のリスク
スタッフ間のコミュニケーション不足は、単に「雰囲気が悪い」だけでは済みません。
患者満足度の低下
スタッフ間の連携ミスは、予約の重複、患者さんへの説明不足、会計ミス、待ち時間の増大に直結します。また、受付と歯科医師で言っていることが違ったり、スタッフ同士がギスギスした雰囲気で会話していたりする様子は、患者さんに即座に伝わり、「この医院は大丈夫か」と不安を与えます。
医療ミスの誘発
「たぶんこうだろう」という思い込みや、ヒヤリハット(ミス寸前の出来事)の共有不足が、重大な医療ミスを引き起こす可能性があります。「あの患者さんはアレルギーがあるはずだ」といった重要な情報伝達が一つ途切れるだけで、取り返しのつかない事態になりかねません。
スタッフの離職と採用コストの増大
「この医院には自分の居場所がない」「院長に本音を言えない」「頑張っても評価されない」と感じたスタッフは、モチベーションを失い、やがて離職していきます。特に優秀なスタッフほど、この見切りは早い傾向にあります。 一人のスタッフが辞めれば、新たな採用コスト(数十万~)と、慣れるまでの教育コスト、そして残ったスタッフの業務負担増大という、経営に対する三重のダメージが発生します。
スタッフコミュニケーションを活性化させる3つのステップ

ステップ1:コミュニケーションの「場」を強制的に作る
「阿吽の呼吸」は自然には生まれません。意識的に話す機会を仕組み化することが第一歩です。
朝礼・終礼の質を高める: 単なる業務連絡(アポイントの確認など)で終わらせてはいけません。「昨日あった良いこと(患者様からの感謝の声など)」「今日の医院目標」「ヒヤリハットの共有と対策」などを数分でも盛り込みます。スタッフが持ち回りで一言スピーチをするのも、相互理解に繋がります。
定期ミーティングの開催と運営: 月に1回に、診療時間を短縮してでも、全員で医院の課題や改善点について話し合う場を設けます。
(運営のコツ)
- 院長は聞き役に徹し、スタッフの意見を絶対に否定しないこと。(心理的安全性の確保)
- アジェンダ(議題)を事前に共有し、スタッフに考えてきてもらうこと。
- ファシリテーター(司会)や書記をスタッフに任せ、主体性を引き出すこと。
ステップ2:「聞き手」としての院長の姿勢を示す
スタッフが「話しやすい」と感じるかどうかは、院長の姿勢にかかっています。
1on1(個別面談)の定期実施: 月に1回、1人10分~15分でも構いません。定期的にスタッフと1対1で話す時間を設けます。「困っていることはないか」「人間関係で悩んでいないか」と院長から歩み寄ります。 さらに、「今後どんなスキルを身につけたいか」「患者さんに喜んでもらうためにどんなことができるか」といった未来志向の対話を引き出すことで、スタッフのキャリアプランと医院の方向性を擦り合わせることもできます。
「傾聴」と「承認(アクノレッジメント)」: スタッフが話している時は、遮らずに最後まで聞きます。そして、意見の内容に関わらず、まずは「話してくれてありがとう」「そう感じていたんだね」と受け止めることが信頼関係の第一歩です。 さらに、「承認」とは、相手の変化や貢献に気づき、それを具体的に言葉で伝えることです。「〇〇さんが患者様の不安に気づいて声かけしてくれて助かった」「いつも準備を丁寧にしてくれてありがとう」と、日々の行動を具体的に認めることで、スタッフの自己肯定感は高まります。
ステップ3:情報共有のルールを明確にする
「誰に」「何を」「いつまでに」報告・相談すべきかを明確にし、属人化を防ぎます。
情報共有ツールの活用と限界: チャットツールや院内SNSなどを活用すれば、記録が残り、診療時間外でも非同期で連絡が取れるため非常に効率的です。 ただし、テキストは冷たく伝わりがちです。感謝や注意など、感情を伴うコミュニケーションは必ず対面で行うなど、ツールと対面の使い分けが重要です。
「報連相」のハードルを下げる文化づくり: 「こんな小さなことで相談していいのか」とスタッフが悩まないよう、「迷ったら必ず相談する」「判断に迷うことは勝手にやらない」というルールを院長自らが発信し続けます。 何より大切なのは、ミスや悪い報告(クレームなど)があった時です。その時にスタッフ個人を責めるのではなく、「報告してくれてありがとう。どうすれば防げたか皆で考えよう」と、失敗を報告した勇気を称賛し、再発防止の仕組みづくりにつなげる文化を院長が作らなければなりません。
メンバーシップを深めるために

スタッフ一人ひとりが、「自分もこの医院を支える一員なんだ」と実感できることが、医院の結束力を高め、医院への愛着や貢献意欲)に繋がります。
そのために必要なのは、
- スタッフと一緒に医院の目標を考えること(例:「今月は自費率〇〇%を目指そう」「キャンセル率を〇%以下に抑えよう」)
- 小さな成功でも、みんなで喜び合うこと(例:目標達成したらランチ会を開く、サンクスカードを導入してスタッフ間で感謝を伝え合う)
- 院長がスタッフのちょっとした困りごと(体調や家族のことなど)に早めに気づき、声をかけること
こうした小さな積み重ねが、スタッフの「この医院で頑張ろう」という主体性を育て、院長が指示しなくてもスタッフが自ら考えて動く組織風土を醸成していきます。
まとめ
医院全体の組織における環境づくりは、特別なことではありません。特に歯科医院においては、「スタッフコミュニケーション」という土台を固めることが、患者満足度を高め、経営を安定化させる最短ルートです。
いきなり全てを変える必要はありません。まずは「スタッフと同じ方向を向く」ために、院長先生が「忙しい」というオーラを少し抑え、「聞く姿勢」を見せることから始めてみませんか?
経営は「数字」だけではありません。「人」というかけがえのない資産をどう活かすか。もし、スタッフとの関係づくりや、コミュニケーションを基盤とした医院の組織づくりにお悩みなら、私たち「Mr.歯科事務長」がお手伝いできるかもしれません。 ご興味があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の解説者

MOCAL株式会社
菊池 一徳 Kazunori Kikuchi
専門学校卒業後、料理の勉強をするためフランスへ渡り、帰国後は代官山のフレンチレストランでサービスと調理に従事。
その後、カフェプロデュースを手がける会社で店長として店舗運営を経験した後、自ら法人を設立しカフェを創業。大田区のビブグルマン「OTAイチオシグルメ」で最優秀賞を受賞した他、不採算店舗の立て直しコンサルタントとしても活動。M&Aで会社株式を譲渡した後は、再びカフェプロデュースの会社に戻り、ジェネラルマネージャーとして活躍。現場でのホスピタリティやマネジメント、マーケティングの経験を活かして約200名のスタッフを管理し、採用や人事面談も多数実施した経験を持つ。
カフェ業界での経験を活かして、クリニックの課題に寄り添い、悩みや孤独を理解した上でサポートしたいという想いから、MOCAL株式会社に入社。